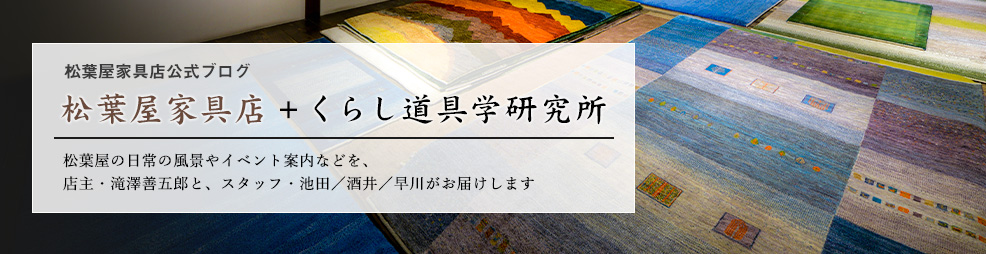ギャッベのことをお話しします。
織り手として知られるカシュガイ族に加えて、「ルリ」という民族をご存知でしょうか。ルリ族はイラン南西部を中心に暮らすイラン系民族で、ギャッベの起源を語る上でカシュガイ族と並んで欠かせない存在です。
カシュガイ族:ギャッベを織る遊牧民の歴史と文化・前編
https://matubaya-kagu.com/blog/archives/8368
遊牧の絨毯に織り込まれた物語 —カシュガイ族の文化と暮らし・後編https://matubaya-kagu.com/blog/archives/8401
あまり知られていないルリ族の歴史や生活について、様々な書籍などを紐解き、僕たちが20年近くギャッベにつきあう間、聞き齧ったことをまとめました。
かなり長い記事になりますが、ゆっくりと一読ください。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ここではルリ族の民族的起源や歴史、文化といった背景をひも解き、クルド人との関係性にも触れながら、ギャッベを織り上げる彼女らの魅力に迫ってみたいと思います。ルリ族の歩みを知ることで、日々目にするギャッベの一枚一枚がさらに愛おしく感じられることでしょう。
- ルリ族とは:南西イランにルーツを持つ民族
- クルド人との関係:共通点と相違点
- イラン南西部の歴史:民族移動と交流の軌跡
- ルリ族とカシュガイ族:遊牧民絨毯に見る交流
- ギャッベとルリ族:遊牧民絨毯文化における役割
- ルリ族の民俗文化:音楽・舞踊・衣装・生活様式
- 現代のルリ族:文化継承と社会における位置づけ
- ルリ族とは:南西イランにルーツを持つ民族
- クルド人との関係:共通点と相違点
- イラン南西部の歴史:民族移動と交流の軌跡
- ルリ族とカシュガイ族:遊牧民絨毯に見る交流
- ギャッベとルリ族:遊牧民絨毯文化における役割
- ルリ族の民俗文化:音楽・舞踊・衣装・生活様式
- 現代のルリ族:文化継承と社会における位置づけ
- 最後に、ルリ族と彼女たちの宝物
ルリ族とは:南西イランにルーツを持つ民族
ルリ族(ルール族とも)は、主にイラン西部から南西部にかけて暮らすイラン系民族です。イラン全人口の約6%を占める比較的大きな集団で、人口は数百万人規模と推計されています。
イランのロレスターン州は「ルリ人の土地」(Lorestan=Lor + stan)という名の通り彼らの故地であり、他にもバフティヤーリー・コフギルーイェなどザグロス山脈沿いの複数の州にまたがって居住しています。さらにフーゼスターン州やファールス州、イーラーム州、ハマダーン州、ブーシェフル州などにも相当数のルリ族が暮らしています。
このようにルリ族は古くからザグロス山脈一帯に広く分布し、自給的な牧畜や絨毯織りを営みながら、現在までその文化を守り続けてきました。
ルリ族の起源と言語
民族的な起源については諸説ありますが、ルリ族は古代からの土着民と、後からイラン高原に来たイラン系遊牧民が混じり合って形成されたと考えられています。例えば古代この地域にいたエラム人やカッシート人の子孫が、中世までにイラン系言語に同化してルリ族の祖先になった可能性が指摘されています。
10世紀以降の史料に「ルール(ルリ)」という名前が現れることから、中世までに現在のルリ族が歴史の表舞台に姿を見せ始めたようです。
一方で、彼ら自身はインド=ヨーロッパ語族に属するイラン系民族であり、その話すルリ語は「中期ペルシア語(パフラヴィー語)の特徴を比較的多く保持する」言語だとも評価されています。これは同じイラン系でも都市のペルシア人とは異なる独自性を保ってきたことの証左と言えるでしょう。
言語としてのルリ語は大きく北部方言と南部方言に二分され、ルレスターン州など北部では「ラーキー(Laki)」と呼ばれる方言を話す人もいます。ルリ語はペルシア語に近い南西イラン語群に属し、一方のラーキーはクルド語に近い特徴を持つと言われます。
実際、ルリ語は中期ペルシア語(パフラヴィー語)から直接発達した言語で、現代ペルシア語(ファールス語)に近縁ですが、単語や発音に独特の風合いがあります。
ルリ族の宗教
宗教は主としてイスラム教シーア派を信仰しており、一部にヤルサン(ヤールサーン、別名アフレ・ハッガー)と呼ばれる神秘主義的な土着宗教を信じる人々もいます。スンナ派のルリ族も少数ながら存在しますが、大部分はシーア派である点は、スンナ派が多いクルド人との大きな違いです。
クルド人との関係:共通点と相違点
ルリ族はしばしば北西イランを中心に分布するクルド人と比較されます。同じインド=ヨーロッパ語系で山岳地帯に暮らし、羊や山羊を遊牧する伝統的生活様式を持つことから、文化的にも共通点が多いのです。
歴史的にも、中世のペルシャ文献では遊牧民全般を指して「クルド(アクラード)」と呼ぶ例もあり、ルリ族が古い時代にはクルドの一部と見做された可能性もあります。
実際、「ルリ族はもともとクルド族の一派で、1000年ほど前に分かれた」との仮説も諸説の一つとして存在しますが、遺伝学・言語学データはルリ族を独立系統とみる傾向が強く、研究者間で合意は得られていません。
言語の違い
一方で言語学的には両者に明確な差があり、ルリ語は前述のようにペルシア語に近い南西群なのに対し、クルド語は北西イラン語群に属します。例えば新年の挨拶で比較すると、クルド語で「Newroz pîroz be」(ノウローズ・ピローズ・ベ)と言うところ、ルリ語では「Neruz mărek ba…」のように表現が異なり(意訳: 良い新年を)、ルリ語がクルド語よりも音や語彙の上でペルシア語に近いことが分かります。
宗教の違い
また宗教面でも違いがあります。イラン国内のクルド人はスンナ派イスラム(シャーフィイー法学派)が多く、少数派としてヤルサン教徒やシーア派クルド人(例えばイーラーム州やケルマーンシャー州のフェイリー・クルドなど)もいます。
これに対しルリ族の大多数は十二イマーム派のシーア派信徒であり、この点で隣接するクルド人社会とは宗教的アイデンティティが異なります。ただし両者ともヤルサン(別名アレヴィー、ヤールサーン)信仰を持つ集団が一部存在するなど、民間信仰のレベルでは共通の伝統も見られます。
文化的気質と社会慣習
文化的な気質について、興味深い指摘として「ルリ族は、クルド族と並んで今日まで生き残った最古のペルシャ系部族」とされることがあります。それだけ古い伝統を守っているという意味ですが、同時に「古来より勇猛果敢で、時の王朝にも一目置かれた存在」とも評されます。
歴史上、クルド人もルリ族も山岳の戦士として知られ、時に王権に反抗し時に傭兵や騎兵隊として活躍しました。19世紀カジャール朝では、バフティヤーリやクルドの騎兵も重要だったが、実際にはトルクメンやカジャール自身を含む多様な部族騎兵が動員されていました。
このように戦士気質や自由を愛する部族性は両者に共通していますが、ルリ族の女性は比較的自由度が高く社会参加が活発だとも言われます。英国ブリタニカ百科事典も「ルリ族の女性はクルド族やバフティヤーリ族の女性と同様、他のペルシャ系やアラブ系の女性よりも伝統的に自由な地位を享受してきた」と指摘しています。
実際、ルリ族社会では女性が家畜の放牧から絨毯織りまで多くの労働を担い、意思決定にも関わる場面が多く見られます。こうした点は、男性優位の色彩が強い中東地域にあってルリ族文化の特徴と言えるでしょう。
総じて、ルリ族とクルド人は「兄弟民族」とも呼べる近しい関係にありますが、言語・宗教・自己認識においては明確な違いがあります。現在のルリ族は自らをクルド人とは別の民族と認識しており、イラン国家の中の一民族集団としてのアイデンティティを持っています。それでも、雄大なザグロスの山並みに抱かれ、伝統的な生活を営んできたという共通の歴史遺産が、両者の文化に通底することは確かです。
イラン南西部の歴史:民族移動と交流の軌跡
ルリ族の故地であるイラン南西部(ザグロス山脈西麓)は、太古の昔から様々な民族が往来し交錯した土地柄です。考古学的には4万年前の旧石器時代から人類定住の痕跡があり、その後青銅器時代にかけて文明が発達しました。
紀元前3000年頃にはこの地に最古級の王朝であるエラム人の国家が成立し、続いて紀元前2千年紀にはカッシート人(カッシ人)がルリスタン一帯に居住していたことが知られています。カッシートはメソポタミアでバビロニア王朝を興すなど活躍し、青銅器文化の遺産(ルリスタン青銅器として有名)を現在に残しました。
民族の融合と言語の変遷
やがて紀元前1千年紀に入り、北方からイラン系遊牧民(古代ペルシア人やメディア人)が南下してくると、これら先住民のエラム系・カッシート系の人々は徐々にイラン化(言語・文化のイラン系化)していきます。
ルリ族の祖先もこの流れの中で生まれたと考えられており、前述したように「古代エラム人がイラン化したもの」という説はその典型例です。つまりルリ族は、古代オリエントの文明を担った人々と、インド・ヨーロッパ語を携えてきた遊牧民との融合によって誕生したと言えるかもしれません。
歴代帝国の支配と地方政権の台頭
その後、この地域はアケメネス朝・パルティア朝・ササン朝といったイランの大帝国の版図に組み込まれていきます。ササン朝時代にはルリ族の本拠地ルリスタンに王族が特別な関心を払ったとの記録もあり、そのためか西部イランにはこの時代の建築物遺跡も多く残っています。
7世紀のイスラム勢力の侵入時、ルリ地域の人々も他のイラン人と共に抵抗しましたが、結局イスラム化は避けられず、以後ルリ族もイスラム文化圏の一部となりました。
ただし9世紀頃からイラン各地で地方政権が台頭し始め、ルリスタン地方も独自の統治者により「ルリスターン」(ルリ人の土地)として認識されるようになります。10世紀半ばに北イラン出身のブワイフ朝がこの地を制圧した際、すでに「ルリスターン」と総称されるルリ人居住地が広がっていた記録があり、中世にルリ族の存在が明確になっていたことが伺えます。
小ルリと大ルリの区分
のちにルリスタンは「小ルリ」(Lur-i-Kuchek)と「大ルリ」(Lur-i-Bozorg)の二つに分けられ、それぞれ現在のロレスターン州+イーラーム州周辺、そしてバフティヤーリ地方+コフギルーイェ・ブーイェルアフマド州+ファールス州北部ママサニ地区などに相当しました。
この区分は中世以降のルリ族諸部族の分布と勢力を反映したもので、「小ルリ」には後述するラク族(ラーク)など北部ルリ系、「大ルリ」には南部のバフティヤーリ族やママサニ族などが含まれていました。
外部民族の流入と多民族モザイク
中世以降、外部からこの地域への民族移動もありました。11世紀、中央アジアからセルジューク朝のトルコ系遊牧民がイラン高原に侵入すると、一部のテュルク系遊牧民がルリスタン南部(大ルリのクフギル地域)にも定住しました。
さらに16世紀のサファヴィー朝時代には、国境防衛や部族支配の都合から他地域の部族を強制移住させる政策が取られ、ザグロスの人里離れた地に多くのトルコ系・クルド系部族が移住させられています。
例えばクルド人の一部族であるセルセレ(サルサル)族は本来ケルマーンシャー近郊の出身でしたが、1590年代にルリスタン方面へ強制移住させられ、在地のデルファン族とともにルリスタン君主に仕える騎兵部隊を形成したといいます。
このように歴代王朝はルリ族の地に外来部族を入植させ、相互の勢力を牽制させる策を講じました。その結果、ルリ族の居住地にはクルド系、アラブ系、そしてテュルク系(トルコ系)の遊牧民グループが点在し、多言語多文化のモザイク状の様相を呈するようになりました。
ルリ族の伝統的生活と織物文化
そうした多民族混在の中でも、ルリ族自身はザグロス山脈の険しい山岳と肥沃な高原に根を下ろし、比較的自治的な生活を営んできました。18~19世紀には欧米の探検家たちがルリスタンを訪れ、部族の一覧や遊動経路について記録を残しています。
彼らの報告によると、当時ルリ族の主な収入源はラクダやラバの飼育および交易で、中でも「絨毯や織物(鞍袋や馬具類)を製造し、市場に供給している」ことが記されています。
19世紀の英国人ローリンソンは「黒ヤギの毛で織ったテント、馬具、そして敷物類──そのほとんど全てが女性たちの手になるものだ」と述べ、男性は家畜の放牧や護衛に従事する一方で、織物製作は主に女性の役割であったと伝えています。
これは現在のルリ族にも通じる特徴で、家内産業としての絨毯織りは伝統的に女性の仕事でした。こうした歴史の積み重ねが、後に世界的に評価されるルリ族の織物文化、すなわちギャッベの土壌を育んでいったのです。
ルリ族とカシュガイ族:遊牧民絨毯に見る交流
イラン南西部でもう一つ重要な遊牧民グループがカシュガイ族です。カシュガイ族(カシュガーイ、Qashqai)はトルコ系(オグズ系)民族で、16世紀頃に中央アジア方面から現在のファールス州一帯に移り住んだと伝えられています。
彼らはシラーズを中心に夏は高原、冬は沿岸部へと年2回の大規模な移動(垂直移動)をする遊牧民として知られ、19世紀には数十万人規模の大遊動を行っていたといいます。カシュガイ族もまた織物文化が豊かで、特に細かな幾何学文様の絨毯で高名でした。
しかし彼らの生活地には古くから在地のルリ系諸部族も多く共存しており、実際ファールス州周辺ではカシュガイ族・ルリ族・アラブ系部族など複数の民族集団が入り混じって遊牧生活を送っていました。
織物文化の相互影響
こうした近接した暮らしの中で、ルリ族とカシュガイ族のあいだには織物技術や意匠のやりとりがあったと考えられます。現に19世紀の絨毯の中には「一見カシュガイの代表柄に見えるが、実はルリ族の作品」という例も見つかります。
米ジョージア美術館の解説によれば、ファールス州に居たルリ族の織物にはカシュガイの典型文様が取り入れられているものがあり、これらは部族間でデザインが旅をした好例だといいます。例えばカシュガイ族とルリ族双方で織られた「ライオン絨毯」がその一例です。
ライオンを大きく一頭、絨毯中央に描く大胆な意匠は19世紀頃に南部ルリ族やカシュガイ族で流行したもので、現在もその伝統は受け継がれています。このように、隣り合う部族同士が互いの文様や技術に影響を及ぼし合うことは珍しくなく、ルリ族とカシュガイ族もその例外ではありませんでした。
社会組織の違い
もっとも社会組織的には、カシュガイ族が複数の部族連合から成る「カシュガイ連合」を形成していたのに対し、ルリ族はそれほど明確な連合体を組まず比較的自律的な部族単位でまとまっていた点で異なります。
南部ルリ族の大きな支流であるバフティヤーリ族は独自のハン(首長)を戴き勢力をふるいましたし、他にもママサニ族やボイヤーアフマド族などがいましたが、カシュガイのように明確な統合政体にはならず、緩やかなネットワークに留まっていたようです。
しかし織物文化という面では、そうした政治的枠組みを超えて女性たちが自由に創意を凝らし、時には隣の民族の図案も取り入れながら、美しい絨毯を織り上げていったのです。
ギャッベとルリ族:遊牧民絨毯文化における役割
ギャッベ(Gabbeh)はペルシャ絨毯の中でも素朴な長い毛足を持つタイプの手織り絨毯で、その名はペルシア語で「粗野な、自然な」という意味に由来します。元々はザグロス山中を移動生活する遊牧民たち──例えばカシュガイ族やルリ族──が、日常の寝具として羊毛をざっくり織り上げた敷物に始まったとされます。
実際、ギャッベという語はルリ語やクルド語では「ガヴァ」と呼ばれ、バフティヤーリ(ルリ系)では「ヘルサク(熊の子)」とも称される独自の呼称を持っています。このことからも、ギャッベがルリ族を含む複数のザグロス系部族に共有される文化であることが分かります。
ギャッベの歴史的評価と時代による変化
歴史的に見れば、19世紀頃までギャッベは素朴な日用品と見なされ、イラン本国の絨毯市場では「ギャッベ=ガベ(英語のガベージ=ゴミに通じる語音)」と評されるほど評価が高くないものでした。
しかし遊牧民の間では丈夫で保温性が高く、敷けばふかふかと柔らかいため重宝されてきたのです。ルリ族の女性たちは自ら紡いだ羊毛糸を草木で染め上げ、幾何学模様や動物のモチーフを即興で織り込みながら、家族のための一枚を丹念に織り上げました。
ギャッベの特徴と製作過程
文様はきっちり図案化されたものではなく、織り手の感性に委ねられます。たとえば鹿やヤギなど身近な動物、小さな花模様、生命の樹といったモチーフが自由奔放に配置され、色彩も黄や赤など鮮やかな原色が大胆に使われます。
そうした伸びやかなデザインの背景には、都市工房の絨毯のように事前に設計図(カルチューム)が存在せず、すべて織り手の頭の中にあるイメージで織られる点が関係しています。結果、世界に二つと同じものが無い、まさに織り手の”物語”が込められた一枚が出来上がるのです。
ギャッベの世界的評価と現代への継承
とはいえギャッベは決して外部に流通しなかったわけではありません。前節で述べたように、19世紀のルリ族は既に絨毯や袋物を交易品としていましたし、20世紀に入ってからは各地のバザールで部族絨毯(トライバル・ラグ)として少量ながら取引されていました。
転機が訪れたのは1970~80年代、イラン出身の美術家パルヴィーズ・タナヴォリらがギャッベに注目し、その素朴な美を再評価し始めたことです。特に1980年代、ゾランヴァリ(Zollanvari)という絨毯商の家系がルリ族やカシュガイ族の織り手に働きかけ、ギャッベを本格的に紹介しました。
彼らは伝統的ギャッベに植物染料を使った新しい色彩やモダンな図案を取り入れ、ヨーロッパの市場で売り出したのです。すると「プリミティブでありながらモダンなアートのようだ」とギャッベは次第に脚光を浴び、1990年代以降、日本を含む世界各国で人気が高まっていきました。
このブームの陰には無名のルリ族女性たちの手仕事があり、彼女たちが代々受け継いできた技とセンスが、現代の絨毯愛好家たちを魅了しているのです。
ルリ族の民俗文化:音楽・舞踊・衣装・生活様式
ルリ族の文化は絨毯だけではありません。遊牧民らしい豊かな民俗芸能や独特の衣装、生活習慣を持っています。
伝統的な舞踊:ハンカチ踊り
例えばルリ族の舞踊として有名なのが「ハンカチ踊り」です。結婚式や新年祭(ノウルーズ)など祝いの席で女性たちが色とりどりのスカーフやハンカチを手に踊るもので、輪になった踊り手が軽快な太鼓やフィドルの調べに合わせ、鮮やかな布をひらひらと振りながらステップを踏みます。
これを現地語で「ダスマール・バーズィー(ハンカチ遊び)」と呼び、ゆったりしたリズムから次第にテンポを上げていく即興性の高い踊りです。右へ左へと三歩ずつ踏む「セパ」や二歩で刻む最速の「ドゥパ」などバリエーションもあり、総じて輪舞(チェピ)系の集団舞踊に分類されます。
女性たちの艶やかな民族衣装と相まって、その舞う姿は圧巻です。打楽器のトンバクやフレームドラム、擦弦楽器のカマンチェ、そしてズルナーという双簧管(チャルメラに似た笛)の甲高い音色が祝いの場を盛り上げ、老若男女が一体となって夜通し踊り明かす光景も珍しくありません。
ルリ族のみならずクルド系やラク系の人々も同様の踊りを伝えており、ザグロスの山々にこだまするその歌声と足拍子は、人々の連帯感を育んできたのです。
鮮やかな民族衣装
衣装にもルリ族の美意識が表れています。伝統的なルリ族女性の衣装は非常にカラフルで重ね着が特徴です。長袖のブラウスにたっぷりと幅のあるスカートを何枚も重ね(下に穿くスカートを重ねるほど裕福とされました)、頭には「ゴルヴァーニ」と呼ばれる大判のスカーフを巻きます。
ゴルヴァーニは絹や木綿でできた鮮やかなスカーフで、ルリスタンの伝統衣装の象徴として近年イランの無形文化遺産にも指定されました。既婚女性はこれに加えてカラフルなベールで髪を覆い、耳飾りや首飾りなど伝統的な銀細工の装身具を身に着けます。
男性はというと、白や生成りのシャツにゆったりしたパンツを履き、上からチョッガ(Chugha)という厚手のウール製マントを羽織ります。頭には黒や茶のフェルト帽をかぶることが多く、かつてはその帽子に女性のゴルヴァーニを巻いて装飾する習慣もあったそうです。
南部ルリ系のバフティヤーリ族では男性用のフェルト帽「コラ」がトレードマークとなっており、女性は逆に黒いスカーフ姿が多いなど地域差もありますが、総じて「鮮やかな女性衣装」と「質実な男性衣装」という対照が興味深い点です。
遊牧の生活様式と住まい
生活様式としては、20世紀中頃までは多くのルリ族が半遊牧民的な暮らしを送っていました。春から夏にかけて山地の高原で放牧し、冬は山麓の村に下りて定住する、といった季節移動を行う家族も多かったのです。
特に南部バフティヤーリ族は20万規模で年2回の大移動を行っていた記録があり、彼らは伝統的な黒いテント「シヤー・チャードル(黒天幕)」で暮らしました。このテントはヤギの毛で織った厚手の織物でできており、防水性が高く雨風をしのげる優れものです。
テント内部には毛織物の敷物や袋が並び、家財道具は必要最小限、まさに移動に適した簡素な生活空間でした。一方で、テントから一歩外に出れば四方に羊やヤギの群れ、遠くには雪をいただくザグロスの峰々という雄大な環境です。そこで奏でられる牧歌(ローリやララバイ)や、夕暮れに囲む炉端での語らいなど、遊牧民の生活は自然と文化が融合した豊かなものでした。
現代に受け継がれる伝統文化
今日では多くのルリ族が定住化し、都市や村で暮らすようになりましたが、それでもなお彼らの民俗文化は脈々と受け継がれています。音楽ではルリ族独自の叙事詩的なバラードや恋歌が伝わり、結婚式では今もハンカチ踊りが欠かせません。
衣装も日常では洋装化が進んだものの、祭礼の際には若い女性たちが伝統ドレスに身を包む光景が各地で見られます。こうしたルリ族の民俗文化は、彼らが織り成すギャッベの文様や色彩感覚にも少なからず影響を与えているでしょう。
たとえばギャッベにしばしば登場するヤギや鳥のモチーフは、彼らの生活と自然が切り離せないことを物語っています。ルリ族の文化を知ることで、ギャッベに描かれた素朴な模様一つひとつにも、彼らの暮らしの息吹や祈りが込められていることに気付くのです。
現代のルリ族:文化継承と社会における位置づけ
現代イランにおいて、ルリ族はペルシア人・アゼルバイジャン人・クルド人に次ぐ第四のエスニックグループと位置付けられています。
社会的・政治的位置づけ
政治的には特定の自治州を持つわけではなく(ロレスターン州知事などにルリ族出身者が就く程度)、民族党も存在しません。そのため国内では他のイラン人と融和的に暮らし、多くは学校や職場でペルシア語を使いこなすバイリンガルです。
しかし、彼らは自分たちのルリ語や伝統を誇りに思っており、近年ではその文化保存にも力が入れられています。例えば2018年(1397年)にはルリ族男女の伝統衣装がイランの国家無形文化遺産に登録されました。これはカシュガイやクルドなど他の少数民族衣装と並ぶ快挙で、国としてもルリ族文化の価値を認め保護しようという動きの表れです。
近代化と生活様式の変容
一方で社会経済的な変化により、ルリ族の伝統的暮らしは大きく姿を変えました。パフラヴィー朝のレザー・シャー統治下(1920~30年代)には強制的な定住化政策が取られ、遊牧民たちは平地の村へと移住させられました。
これは徴税や統治を円滑にするためでしたが、結果として多くの部族が従来の自由な遊牧を失い、生活基盤を強制的に変えられることになりました。ルリ族も例外ではなく、一部反発も起きましたが、時代の流れの中で定住と近代化を受け入れていきました。
そのため現在、季節移動を続ける純粋な遊牧民ルリ族はごく少数で、大半は農業や牧畜を営みつつ村や町に腰を落ち着けています。しかし彼らの文化的アイデンティティは失われておらず、家庭内でルリ語が話され、祝い事では伝統の歌や踊りが披露されます。
21世紀におけるギャッベ織りの継承
また絨毯織りも依然として重要な生業です。特にカシュガイ族との交流地帯であったファールス州では、21世紀の今日もルリ族の女性たちが家内工業的にギャッベを織り続けています。それらは組合や企業を通じて日本にも輸出され、私たちの暮らしを彩ってくれているのです。
ギャッベに込められた物語
最後に、ルリ族とギャッベの関係に改めて思いを馳せてみましょう。かつては素朴な日用品として評価されていなかったギャッベがこれほど世界に愛されるようになった背景には、ルリ族をはじめとする部族の女性たちの存在がありました。
紡いだ糸の手触りや染めた草木の色合いを感じ取りながら、一結び一結びに家族への愛情や自然への畏敬を込めて織り上げる…。そんな彼女たちのまなざしがあったからこそ、ギャッベは温もりと味わいに満ちた作品となり得たのです。
ルリ族はギャッベの「生みの親」であり、その文様に宿る物語の語り部でもあります。もしお手元にギャッベがおありなら、ぜひ次回眺める際には遠いザグロスの山村で働くルリ族の女性の姿に思いを馳せてみてください。
きっと、ギャッベに織り込まれた草花や動物たちが、彼女たちの声となって見る者に何かを語りかけてくれることでしょう。# ギャッベの織り手である、ルリ族:ギャッベの起源とされる部族、歴史、文化、クルドとの関係
ギャッベと呼ばれるペルシャ絨毯は、素朴で温かみのある意匠で日本でも人気を博していますが、その織り手として知られるルリ族という民族をご存知でしょうか。ルリ族はイラン南西部を中心に暮らすイラン系民族で、ギャッベの起源を語る上で欠かせない存在です。本記事ではルリ族の民族的起源や歴史、文化といった背景をひも解き、クルド人との関係性にも触れながら、ギャッベを織り上げる彼らの魅力に迫ってみたいと思います。ルリ族の歩みを知ることで、日々目にするギャッベの一枚一枚がさらに愛おしく感じられることでしょう。
ルリ族とは:南西イランにルーツを持つ民族
ルリ族(ルール族とも)は、主にイラン西部から南西部にかけて暮らすイラン系民族です。イラン全人口の約6%を占める比較的大きな集団で、人口は数百万人規模と推計されています。イランのロレスターン州は「ルリ人の土地」(Lorestan=Lor + stan)という名の通り彼らの故地であり、他にもバフティヤーリー・コフギルーイェなどザグロス山脈沿いの複数の州にまたがって居住しています。さらにフーゼスターン州やファールス州、イーラーム州、ハマダーン州、ブーシェフル州などにも相当数のルリ族が暮らしています。このようにルリ族は古くからザグロス山脈一帯に広く分布し、自給的な牧畜や絨毯織りを営みながら、現在までその文化を守り続けてきました。
民族的な起源については諸説ありますが、ルリ族は古代からの土着民と、後からイラン高原に来たイラン系遊牧民が混じり合って形成されたと考えられています。例えば古代この地域にいたエラム人やカッシート人の子孫が、中世までにイラン系言語に同化してルリ族の祖先になった可能性が指摘されています。10世紀以降の史料に「ルール(ルリ)」という名前が現れることから、中世までに現在のルリ族が歴史の表舞台に姿を見せ始めたようです。
一方で、彼ら自身はインド=ヨーロッパ語族に属するイラン系民族であり、その話すルリ語は「中期ペルシア語(パフラヴィー語)の特徴を比較的多く保持する」言語だとも評価されています。これは同じイラン系でも都市のペルシア人とは異なる独自性を保ってきたことの証左と言えるでしょう。
言語としてのルリ語は大きく北部方言と南部方言に二分され、ルレスターン州など北部では「ラーキー(Laki)」と呼ばれる方言を話す人もいます。ルリ語はペルシア語に近い南西イラン語群に属し、一方のラーキーはクルド語に近い特徴を持つと言われます。実際、ルリ語は中期ペルシア語(パフラヴィー語)から直接発達した言語で、現代ペルシア語(ファールス語)に近縁ですが、単語や発音に独特の風合いがあります。宗教は主としてイスラム教シーア派を信仰しており、一部にヤルサン(ヤールサーン、別名アフレ・ハッガー)と呼ばれる神秘主義的な土着宗教を信じる人々もいます。スンナ派のルリ族も少数ながら存在しますが、大部分はシーア派である点は、スンナ派が多いクルド人との大きな違いです。
クルド人との関係:共通点と相違点
ルリ族はしばしば北西イランを中心に分布するクルド人と比較されます。同じインド=ヨーロッパ語系で山岳地帯に暮らし、羊や山羊を遊牧する伝統的生活様式を持つことから、文化的にも共通点が多いのです。歴史的にも、中世のペルシャ文献では遊牧民全般を指して「クルド(アクラード)」と呼ぶ例もあり、ルリ族が古い時代にはクルドの一部と見做された可能性もあります。
実際、「ルリ族はもともとクルド族の一派で、1000年ほど前に分かれた」との仮説も諸説の一つとして存在しますが、遺伝学・言語学データはルリ族を独立系統とみる傾向が強く、研究者間で合意は得られていません。一方で言語学的には両者に明確な差があり、ルリ語は前述のようにペルシア語に近い南西群なのに対し、クルド語は北西イラン語群に属します。例えば新年の挨拶で比較すると、クルド語で「Newroz pîroz be」(ノウローズ・ピローズ・ベ)と言うところ、ルリ語では「Neruz mărek ba…」のように表現が異なり(意訳: 良い新年を)、ルリ語がクルド語よりも音や語彙の上でペルシア語に近いことが分かります。
また宗教面でも違いがあります。イラン国内のクルド人はスンナ派イスラム(シャーフィイー法学派)が多く、少数派としてヤルサン教徒やシーア派クルド人(例えばイーラーム州やケルマーンシャー州のフェイリー・クルドなど)もいます。これに対しルリ族の大多数は十二イマーム派のシーア派信徒であり、この点で隣接するクルド人社会とは宗教的アイデンティティが異なります。ただし両者ともヤルサン(別名アレヴィー、ヤールサーン)信仰を持つ集団が一部存在するなど、民間信仰のレベルでは共通の伝統も見られます。
文化的な気質について、興味深い指摘として「ルリ族は、クルド族と並んで今日まで生き残った最古のペルシャ系部族」とされることがあります。それだけ古い伝統を守っているという意味ですが、同時に「古来より勇猛果敢で、時の王朝にも一目置かれた存在」とも評されます。歴史上、クルド人もルリ族も山岳の戦士として知られ、時に王権に反抗し時に傭兵や騎兵隊として活躍しました。19世紀カジャール朝では、バフティヤーリやクルドの騎兵も重要だったが、実際にはトルクメンやカジャール自身を含む多様な部族騎兵が動員されていました。
このように戦士気質や自由を愛する部族性は両者に共通していますが、ルリ族の女性は比較的自由度が高く社会参加が活発だとも言われます。英国ブリタニカ百科事典も「ルリ族の女性はクルド族やバフティヤーリ族の女性と同様、他のペルシャ系やアラブ系の女性よりも伝統的に自由な地位を享受してきた」と指摘しています。実際、ルリ族社会では女性が家畜の放牧から絨毯織りまで多くの労働を担い、意思決定にも関わる場面が多く見られます。こうした点は、男性優位の色彩が強い中東地域にあってルリ族文化の特徴と言えるでしょう。
総じて、ルリ族とクルド人は「兄弟民族」とも呼べる近しい関係にありますが、言語・宗教・自己認識においては明確な違いがあります。現在のルリ族は自らをクルド人とは別の民族と認識しており、イラン国家の中の一民族集団としてのアイデンティティを持っています。それでも、雄大なザグロスの山並みに抱かれ、伝統的な生活を営んできたという共通の歴史遺産が、両者の文化に通底することは確かです。
イラン南西部の歴史:民族移動と交流の軌跡
ルリ族の故地であるイラン南西部(ザグロス山脈西麓)は、太古の昔から様々な民族が往来し交錯した土地柄です。考古学的には4万年前の旧石器時代から人類定住の痕跡があり、その後青銅器時代にかけて文明が発達しました。紀元前3000年頃にはこの地に最古級の王朝であるエラム人の国家が成立し、続いて紀元前2千年紀にはカッシート人(カッシ人)がルリスタン一帯に居住していたことが知られています。カッシートはメソポタミアでバビロニア王朝を興すなど活躍し、青銅器文化の遺産(ルリスタン青銅器として有名)を現在に残しました。
やがて紀元前1千年紀に入り、北方からイラン系遊牧民(古代ペルシア人やメディア人)が南下してくると、これら先住民のエラム系・カッシート系の人々は徐々にイラン化(言語・文化のイラン系化)していきます。ルリ族の祖先もこの流れの中で生まれたと考えられており、前述したように「古代エラム人がイラン化したもの」という説はその典型例です。つまりルリ族は、古代オリエントの文明を担った人々と、インド・ヨーロッパ語を携えてきた遊牧民との融合によって誕生したと言えるかもしれません。
その後、この地域はアケメネス朝・パルティア朝・ササン朝といったイランの大帝国の版図に組み込まれていきます。ササン朝時代にはルリ族の本拠地ルリスタンに王族が特別な関心を払ったとの記録もあり、そのためか西部イランにはこの時代の建築物遺跡も多く残っています。7世紀のイスラム勢力の侵入時、ルリ地域の人々も他のイラン人と共に抵抗しましたが、結局イスラム化は避けられず、以後ルリ族もイスラム文化圏の一部となりました。
ただし9世紀頃からイラン各地で地方政権が台頭し始め、ルリスタン地方も独自の統治者により「ルリスターン」(ルリ人の土地)として認識されるようになります。10世紀半ばに北イラン出身のブワイフ朝がこの地を制圧した際、すでに「ルリスターン」と総称されるルリ人居住地が広がっていた記録があり、中世にルリ族の存在が明確になっていたことが伺えます。のちにルリスタンは「小ルリ」(Lur-i-Kuchek)と「大ルリ」(Lur-i-Bozorg)の二つに分けられ、それぞれ現在のロレスターン州+イーラーム州周辺、そしてバフティヤーリ地方+コフギルーイェ・ブーイェルアフマド州+ファールス州北部ママサニ地区などに相当しました。この区分は中世以降のルリ族諸部族の分布と勢力を反映したもので、「小ルリ」には後述するラク族(ラーク)など北部ルリ系、「大ルリ」には南部のバフティヤーリ族やママサニ族などが含まれていました。
中世以降、外部からこの地域への民族移動もありました。11世紀、中央アジアからセルジューク朝のトルコ系遊牧民がイラン高原に侵入すると、一部のテュルク系遊牧民がルリスタン南部(大ルリのクフギル地域)にも定住しました。さらに16世紀のサファヴィー朝時代には、国境防衛や部族支配の都合から他地域の部族を強制移住させる政策が取られ、ザグロスの人里離れた地に多くのトルコ系・クルド系部族が移住させられています。
例えばクルド人の一部族であるセルセレ(サルサル)族は本来ケルマーンシャー近郊の出身でしたが、1590年代にルリスタン方面へ強制移住させられ、在地のデルファン族とともにルリスタン君主に仕える騎兵部隊を形成したといいます。このように歴代王朝はルリ族の地に外来部族を入植させ、相互の勢力を牽制させる策を講じました。その結果、ルリ族の居住地にはクルド系、アラブ系、そしてテュルク系(トルコ系)の遊牧民グループが点在し、多言語多文化のモザイク状の様相を呈するようになりました。
そうした多民族混在の中でも、ルリ族自身はザグロス山脈の険しい山岳と肥沃な高原に根を下ろし、比較的自治的な生活を営んできました。18~19世紀には欧米の探検家たちがルリスタンを訪れ、部族の一覧や遊動経路について記録を残しています。彼らの報告によると、当時ルリ族の主な収入源はラクダやラバの飼育および交易で、中でも「絨毯や織物(鞍袋や馬具類)を製造し、市場に供給している」ことが記されています。19世紀の英国人ローリンソンは「黒ヤギの毛で織ったテント、馬具、そして敷物類──そのほとんど全てが女性たちの手になるものだ」と述べ、男性は家畜の放牧や護衛に従事する一方で、織物製作は主に女性の役割であったと伝えています。これは現在のルリ族にも通じる特徴で、家内産業としての絨毯織りは伝統的に女性の仕事でした。こうした歴史の積み重ねが、後に世界的に評価されるルリ族の織物文化、すなわちギャッベの土壌を育んでいったのです。
ルリ族とカシュガイ族:遊牧民絨毯に見る交流
イラン南西部でもう一つ重要な遊牧民グループがカシュガイ族です。カシュガイ族(カシュガーイ、Qashqai)はトルコ系(オグズ系)民族で、16世紀頃に中央アジア方面から現在のファールス州一帯に移り住んだと伝えられています。彼らはシラーズを中心に夏は高原、冬は沿岸部へと年2回の大規模な移動(垂直移動)をする遊牧民として知られ、19世紀には数十万人規模の大遊動を行っていたといいます。カシュガイ族もまた織物文化が豊かで、特に細かな幾何学文様の絨毯で高名でした。しかし彼らの生活地には古くから在地のルリ系諸部族も多く共存しており、実際ファールス州周辺ではカシュガイ族・ルリ族・アラブ系部族など複数の民族集団が入り混じって遊牧生活を送っていました。
こうした近接した暮らしの中で、ルリ族とカシュガイ族のあいだには織物技術や意匠のやりとりがあったと考えられます。現に19世紀の絨毯の中には「一見カシュガイの代表柄に見えるが、実はルリ族の作品」という例も見つかります。米ジョージア美術館の解説によれば、ファールス州に居たルリ族の織物にはカシュガイの典型文様が取り入れられているものがあり、これらは部族間でデザインが旅をした好例だといいます。例えばカシュガイ族とルリ族双方で織られた「ライオン絨毯」がその一例です。ライオンを大きく一頭、絨毯中央に描く大胆な意匠は19世紀頃に南部ルリ族やカシュガイ族で流行したもので、現在もその伝統は受け継がれています。このように、隣り合う部族同士が互いの文様や技術に影響を及ぼし合うことは珍しくなく、ルリ族とカシュガイ族もその例外ではありませんでした。
もっとも社会組織的には、カシュガイ族が複数の部族連合から成る「カシュガイ連合」を形成していたのに対し、ルリ族はそれほど明確な連合体を組まず比較的自律的な部族単位でまとまっていた点で異なります。南部ルリ族の大きな支流であるバフティヤーリ族は独自のハン(首長)を戴き勢力をふるいましたし、他にもママサニ族やボイヤーアフマド族などがいましたが、カシュガイのように明確な統合政体にはならず、緩やかなネットワークに留まっていたようです。しかし織物文化という面では、そうした政治的枠組みを超えて女性たちが自由に創意を凝らし、時には隣の民族の図案も取り入れながら、美しい絨毯を織り上げていったのです。
ギャッベとルリ族:遊牧民絨毯文化における役割
ギャッベ(Gabbeh)はペルシャ絨毯の中でも素朴な長い毛足を持つタイプの手織り絨毯で、その名はペルシア語で「粗野な、自然な」という意味に由来します。元々はザグロス山中を移動生活する遊牧民たち──例えばカシュガイ族やルリ族──が、日常の寝具として羊毛をざっくり織り上げた敷物に始まったとされます。実際、ギャッベという語はルリ語やクルド語では「ガヴァ」と呼ばれ、バフティヤーリ(ルリ系)では「ヘルサク(熊の子)」とも称される独自の呼称を持っています。このことからも、ギャッベがルリ族を含む複数のザグロス系部族に共有される文化であることが分かります。
歴史的に見れば、19世紀頃までギャッベは粗雑な日用品と見なされ、イラン本国の絨毯市場では「ギャッベ=ガベ(英語のガベージ=ゴミに通じる語音)」と揶揄されるほど評価が低いものでした。しかし遊牧民の間では丈夫で保温性が高く、敷けばふかふかと柔らかいため重宝されてきたのです。ルリ族の女性たちは自ら紡いだ羊毛糸を草木で染め上げ、幾何学模様や動物のモチーフを即興で織り込みながら、家族のための一枚を丹念に織り上げました。文様はきっちり図案化されたものではなく、織り手の感性に委ねられます。たとえば鹿やヤギなど身近な動物、小さな花模様、生命の樹といったモチーフが自由奔放に配置され、色彩も黄や赤など鮮やかな原色が大胆に使われます。そうした伸びやかなデザインの背景には、都市工房の絨毯のように事前に設計図(カルチューム)が存在せず、すべて織り手の頭の中にあるイメージで織られる点が関係しています。結果、世界に二つと同じものが無い、まさに織り手の”物語”が込められた一枚が出来上がるのです。
とはいえギャッベは決して外部に流通しなかったわけではありません。前節で述べたように、19世紀のルリ族は既に絨毯や袋物を交易品としていましたし、20世紀に入ってからは各地のバザールで部族絨毯(トライバル・ラグ)として少量ながら取引されていました。転機が訪れたのは1970~80年代、イラン出身の美術家パルヴィーズ・タナヴォリらがギャッベに注目し、その素朴な美を再評価し始めたことです。特に1980年代、ゾランヴァリ(Zollanvari)という絨毯商の家系がルリ族やカシュガイ族の織り手に働きかけ、ギャッベを本格的に商品化しました。彼らは伝統的ギャッベに植物染料を使った新しい色彩やモダンな図案を取り入れ、ヨーロッパの市場で売り出したのです。すると「プリミティブでありながらモダンなアートのようだ」とギャッベは次第に脚光を浴び、1990年代以降、日本を含む世界各国で人気が高まっていきました。このブームの陰には無名のルリ族女性たちの手仕事があり、彼女たちが代々受け継いできた技とセンスが、現代の絨毯愛好家たちを魅了しているのです。
ルリ族の民俗文化:音楽・舞踊・衣装・生活様式
ルリ族の文化は絨毯だけではありません。遊牧民らしい豊かな民俗芸能や独特の衣装、生活習慣を持っています。例えばルリ族の舞踊として有名なのが「ハンカチ踊り」です。結婚式や新年祭(ノウルーズ)など祝いの席で女性たちが色とりどりのスカーフやハンカチを手に踊るもので、輪になった踊り手が軽快な太鼓やフィドルの調べに合わせ、鮮やかな布をひらひらと振りながらステップを踏みます。これを現地語で「ダスマール・バーズィー(ハンカチ遊び)」と呼び、ゆったりしたリズムから次第にテンポを上げていく即興性の高い踊りです。右へ左へと三歩ずつ踏む「セパ」や二歩で刻む最速の「ドゥパ」などバリエーションもあり、総じて輪舞(チェピ)系の集団舞踊に分類されます。女性たちの艶やかな民族衣装と相まって、その舞う姿は圧巻です。打楽器のトンバクやフレームドラム、擦弦楽器のカマンチェ、そしてズルナーという双簧管(チャルメラに似た笛)の甲高い音色が祝いの場を盛り上げ、老若男女が一体となって夜通し踊り明かす光景も珍しくありません。ルリ族のみならずクルド系やラク系の人々も同様の踊りを伝えており、ザグロスの山々にこだまするその歌声と足拍子は、人々の連帯感を育んできたのです。
衣装にもルリ族の美意識が表れています。伝統的なルリ族女性の衣装は非常にカラフルで重ね着が特徴です。長袖のブラウスにたっぷりと幅のあるスカートを何枚も重ね(下に穿くスカートを重ねるほど裕福とされました)、頭には「ゴルヴァーニ」と呼ばれる大判のスカーフを巻きます。ゴルヴァーニは絹や木綿でできた鮮やかなスカーフで、ルリスタンの伝統衣装の象徴として近年イランの無形文化遺産にも指定されました。既婚女性はこれに加えてカラフルなベールで髪を覆い、耳飾りや首飾りなど伝統的な銀細工の装身具を身に着けます。男性はというと、白や生成りのシャツにゆったりしたパンツを履き、上からチョッガ(Chugha)という厚手のウール製マントを羽織ります。頭には黒や茶のフェルト帽をかぶることが多く、かつてはその帽子に女性のゴルヴァーニを巻いて装飾する習慣もあったそうです。南部ルリ系のバフティヤーリ族では男性用のフェルト帽「コラ」がトレードマークとなっており、女性は逆に黒いスカーフ姿が多いなど地域差もありますが、総じて「鮮やかな女性衣装」と「質実な男性衣装」という対照が興味深い点です。
生活様式としては、20世紀中頃までは多くのルリ族が半遊牧民的な暮らしを送っていました。春から夏にかけて山地の高原で放牧し、冬は山麓の村に下りて定住する、といった季節移動を行う家族も多かったのです。特に南部バフティヤーリ族は20万規模で年2回の大移動を行っていた記録があり、彼らは伝統的な黒いテント「シヤー・チャードル(黒天幕)」で暮らしました。このテントはヤギの毛で織った厚手の織物でできており、防水性が高く雨風をしのげる優れものです。テント内部には毛織物の敷物や袋が並び、家財道具は必要最小限、まさに移動に適した簡素な生活空間でした。一方で、テントから一歩外に出れば四方に羊やヤギの群れ、遠くには雪をいただくザグロスの峰々という雄大な環境です。そこで奏でられる牧歌(ローリやララバイ)や、夕暮れに囲む炉端での語らいなど、遊牧民の生活は自然と文化が融合した豊かなものでした。
今日では多くのルリ族が定住化し、都市や村で暮らすようになりましたが、それでもなお彼らの民俗文化は脈々と受け継がれています。音楽ではルリ族独自の叙事詩的なバラードや恋歌が伝わり、結婚式では今もハンカチ踊りが欠かせません。衣装も日常では洋装化が進んだものの、祭礼の際には若い女性たちが伝統ドレスに身を包む光景が各地で見られます。こうしたルリ族の民俗文化は、彼らが織り成すギャッベの文様や色彩感覚にも少なからず影響を与えているでしょう。たとえばギャッベにしばしば登場するヤギや鳥のモチーフは、彼らの生活と自然が切り離せないことを物語っています。ルリ族の文化を知ることで、ギャッベに描かれた素朴な模様一つひとつにも、彼らの暮らしの息吹や祈りが込められていることに気付くのです。
現代のルリ族:文化継承と社会における位置づけ
現代イランにおいて、ルリ族はペルシア人・アゼルバイジャン人・クルド人に次ぐ第四のエスニックグループと位置付けられています。政治的には特定の自治州を持つわけではなく(ロレスターン州知事などにルリ族出身者が就く程度)、民族党も存在しません。そのため国内では他のイラン人と融和的に暮らし、多くは学校や職場でペルシア語を使いこなすバイリンガルです。しかし、彼らは自分たちのルリ語や伝統を誇りに思っており、近年ではその文化保存にも力が入れられています。例えば2018年(1397年)にはルリ族男女の伝統衣装がイランの国家無形文化遺産に登録されました。これはカシュガイやクルドなど他の少数民族衣装と並ぶ快挙で、国としてもルリ族文化の価値を認め保護しようという動きの表れです。
一方で社会経済的な変化により、ルリ族の伝統的暮らしは大きく姿を変えました。パフラヴィー朝のレザー・シャー統治下(1920~30年代)には強制的な定住化政策が取られ、遊牧民たちは平地の村へと移住させられました。これは徴税や統治を円滑にするためでしたが、結果として多くの部族が従来の自由な遊牧を失い、生活基盤を強制的に変えられることになりました。ルリ族も例外ではなく、一部反発も起きましたが、時代の流れの中で定住と近代化を受け入れていきました。そのため現在、季節移動を続ける純粋な遊牧民ルリ族はごく少数で、大半は農業や牧畜を営みつつ村や町に腰を落ち着けています。しかし彼らの文化的アイデンティティは失われておらず、家庭内でルリ語が話され、祝い事では伝統の歌や踊りが披露されます。また絨毯織りも依然として重要な生業です。特にカシュガイ族との交流地帯であったファールス州では、21世紀の今日もルリ族の女性たちが家内工業的にギャッベを織り続けています。それらは組合や企業を通じて日本にも輸出され、私たちの暮らしを彩ってくれているのです。
最後に、ルリ族と彼女たちの宝物
静かな大地の上で 時を超えて受け継がれる
ルリ族の女性たちの手が紡ぐ物語です。
かつては単なる日用の織物で、誰も気に留めなかった
ギャッベ。 今や世界中の人々の心を温める宝。
ザグロスの山々に抱かれた村で 羊の毛を紡ぎ、
草木で染め 一結び一結びに想いを込める。
自然への畏敬、家族への愛 女性たちの優しい
指先から生まれる 温もりと深い味わいの芸術。
あなたの手元にあるギャッベを 眺めるときには
はるか遠い山の村の女性の姿を想って
そこに描かれた草花や動物たちが 織り手の魂の声となって
あなたに静かに語りかけてくるでしょう。

僕たちが選んだギャッベに会いに来てください。
『大地と空、 火と草色のじゅうたん 春のギャッベ展』
~ 5月I I 日(日)まで開催中です。
・・・・・・・・・・・・・・
松葉屋がえらび抜いてきた
ギャッベが250枚。
他では見られない
色使い、 柄のものが揃います。
その中からさらにお好きな一枚を
ご自分と、 ご家族のために
おえらびください。

··········