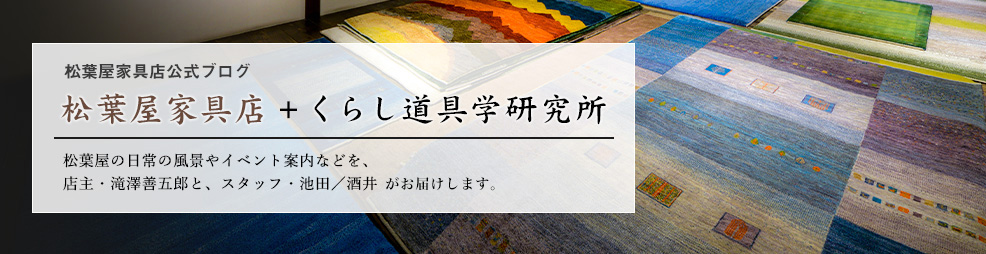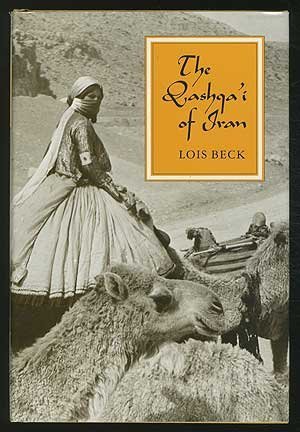こんにちは。
松葉屋家具店の滝澤善五郎です。
僕たちが「ゾランヴァリギャッベ」とお付き合いするようになって、
気づけばもう20年近くが経ちました。
このあいだに、2000人近くのお客様が、僕らが選んだ美しいギャッベを
暮らしの中に迎え入れてくれました。
けれどもふと、思うのです。
このいちまいの敷物の向こうに広がる風景、
織り子さんたちの手の動き、
カシュガイ族の人びとの暮らしや文化について、
どれほど僕らは知っていたのだろうか——と。
ギャッベのふるさと、イランの南西部。
遊牧民カシュガイ族が草原のなかで織り上げるその風景に、
実際に足を運ばせていただいたこともあります。
テントを訪れたり、定住のお家で食事をいただいたり。


 ゾランヴァリさんご兄弟や、カシュガイの織り子さんたち
ゾランヴァリさんご兄弟や、カシュガイの織り子さんたち
(ソマイエ、プーランさんとアリさん)が長野の僕たちの店に
来てくれて、ギャッベを織り上げてくれたこともありました。


そんな断片的な交流の記憶や、聞きかじったこと、読みかじった資料たちを頼りに、今あらためて、ギャッベを生んだ人びとの歴史と文化について、文献などをもとにゆっくり、言葉を綴ってみたいと思います。
長くなるので、前編と後編に分けて投稿します。
今回参考にした文献をお知らせします。
- Beck, Lois (1986). The Qashqa’i of Iran. Yale University Press.
- Beck, Lois (2010). 「The Qashqa’i of Iran」『Cultural Survival Quarterly』8(1).
- Beck, Lois (2014). Nomads in Postrevolutionary Iran: The Qashqa’i in an Era of Change. Routledge.
- Huang, Julia (2014). Tribeswomen of Iran: Weaving Memories among Qashqa’i Nomads. I.B. Tauris.
- Encyclopædia Iranica Online, “Qašqāʾi Tribal Confederacy” (1997).
- 藤井毅(1996)『イラン遊牧民―変貌する牧畜民社会』風響社. (カシュガイ族を含むイラン遊牧民の民族誌研究)

カシュガイ族:ギャッベを織る遊牧民の歴史と文化
前編
起源と歴史的移動
カシュガイ族は、イラン南西部(ファールス州周辺)を中心に遊牧生活を営んできたテュルク系の部族連合である。
彼らは自らの言語を「トルキ」と呼ぶトルコ系(オグズ系)のカシュガイ語を話し、ペルシア語も公用語として使いこなす。
カシュガイ族の起源については、中央アジアのテュルク系遊牧民にさかのぼると伝えられる。
伝承ではフラグ・ハン(フレグ)やティムールの軍勢とともにイラン高原に来たとも言われるが、歴史学的には11世紀頃セルジューク朝時代の大移動で南下し、いったんイラン北西部(アルダビール近郊モガーン平原など)に居住した後、18世紀頃までに現在のファールス地方に定着したと考えられている。
複雑な移住の過程で、カシュガイ族はテュルク系を主体としつつもロル族・クルド人・アラブ人・バルーチ人・ペルシア人系など多様な出自の部族や氏族を包含する連合体へと発展した。
この部族連合(イル・エ・カシュガイ)は18世紀後半、ザンド朝の時代に形成されたとされ、やがてカージャール朝期(19〜20世紀初頭)にはイラン南部で強大な影響力を持つようになる。
19世紀のカシュガイ族は比較的自治権を保ち、カージャール朝の中央政権も彼らを直接統治することは難しかったため、族長(カーン)に徴税や治安維持などを委ねることで間接的に統治していた。
この頃、カシュガイ族の首長一族であるジャニカーン朝(シャーイルー家)は南部イランの名士階層の一角を占め、国内政治や第一次大戦期の国際関係にも影響を及ぼした。
20世紀初頭の立憲革命ではカシュガイ族は革命派を支持し、第一次世界大戦中には英国軍に対する武装抵抗も行っている。
しかしパフラヴィー朝のレザー・シャー(在位1925–41年)は、国家統合と近代化の名の下にカシュガイ族を含む遊牧民への弾圧政策を敷いた。
彼は有力部族長を処刑・投獄・追放し、部族の武装解除と強制定住を断行する。
1930年代、カシュガイ族は伝統的な季節移動を禁じられて不毛の定住地に移され、遊牧・農耕の生計手段を断たれて困窮した。
1941年にレザー・シャーが退位すると、追放されていたカシュガイ族指導者たちは帰国して部族統治を再開し、一時的に遊牧も復活した。
しかしその息子のモハンマド・レザー・シャー治下でも中央政府とカシュガイ族の対立は続き、1950年代には指導者層が再び亡命を余儀なくされた。
1960年代の白色革命(土地改革)では遊牧民の牧地が国有化され、伝統的な放牧権や土地利用権が大きく制限されることとなった。
1979年のイラン革命直後、亡命先から戻った族長ホスロ・ハーンらが武装蜂起を試みたが、革命政権の「イスラム革命防衛隊」により1982年までに鎮圧され、首領は処刑・幽閉された。
こうした激動を経ても、カシュガイ族そのものは消滅せず、イラン南西部において現在も数十万人規模と推定される人々がそのアイデンティティを受け継いでいる。
21世紀の現在、カシュガイ族は完全定住化した人々から季節移動を守る遊牧民まで様々だが、イラン最大級の遊牧民部族としての歴史と文化はなお健在である。
遊牧生活の特徴
カシュガイ族は伝統的に年に二度の大移動(春の北遷・秋の南遷)を行うトランスヒューマンス型の遊牧民である。
冬季は温暖な低地で家畜を越冬させ、夏になるとザグロス山脈の高地牧草地へ数百キロもの距離を移動する。
かつてはシーラーズ近郊の冬営地からペルシア湾岸寄りの夏営地まで南北約480kmに及ぶ往復路を、羊・ヤギの群れとともに徒歩で旅した。
行程は険しく、時に年老いた家族が途中の町に預けられるほど過酷なものだったと伝えられる。
しかしそれだけの距離を移動すれば、真夏でも爽やかな高原で放牧でき、真冬でも暖かな低地で越冬できるため、家畜の繁殖と牧草資源の持続に適っていたのである。
遊牧民にとって四季折々に変わる雄大な山岳風景の中を自由に移動することは、何にも代えがたい喜びでもあった。
現在では国の規制下で定められた移動ルート(遊牧回廊)を通り、トラック輸送も併用しながら移動する者が多いが、それでも季節ごとの移動生活(現地で「クーチ」と呼ばれる)はカシュガイ族文化の核となっている。
遊牧民の伝統的住居は、ヤギの毛で織った黒い天幕(ブラックテント)である。
木の支柱と繊維縄で組み立てるこのテントは可搬性に優れ、大人数にも対応できる柔軟な構造だ。
カシュガイ族の伝統的な黒い天幕。ヤギ毛で織られた布地にカラフルな飾り房が吊るされている。
彼らは季節ごとに天幕を解体・運搬し、高地と低地の野営地を行き来する。
天幕の外観は一見すると素朴だが、内部には美しい織物が敷き詰められ、仕切りや収納も工夫された快適な空間が広がっている。
家族ごとの天幕は冬営地・夏営地の双方で小さなキャンプを形成し、放牧地では一家族または数家族で暮らす。
しかし春秋の長い移動の途上では、盗賊や外敵から身を守るため数十張りもの天幕が集団で隊列を組んで進軍するように旅をしたという。
こうした柔軟な移動・居住形態は、土地と水を求めて環境に合わせ暮らす遊牧民に適したものであり、カシュガイ族はその生活の知恵を長く守り伝えてきた。
カシュガイ族の生業は主に牧畜と農耕のミックスである。
遊牧民たちは羊とヤギの群れを所有し、乳や肉、毛皮といった産物を得てきた。
特に羊毛と山羊毛は後述の織物づくりに不可欠であり、乳から作るヨーグルトやバター、乾燥チーズは彼らの重要な蛋白源である。
副次的にラクダやウマ、ラバ、ロバなどの家畜も荷運びや騎乗に利用された。
冬営地・夏営地では小麦や大麦などの穀物を栽培し、移動中にも山野で燃料や薬草、木の実などの採集を行う。
伝統的主食は自家産小麦で焼く平たいパンであり、各天幕に簡易の土窯を築いて日々の焼きたてパンを欠かさない。
荒く挽いた全粒粉の素朴なパンと、凝乳を発酵させた酸乳(ドゥーグ)や乾燥チーズ、干し肉、野草のスープなどを組み合わせた食事が典型的な献立であった。
物々交換や行商人からの購入で茶・砂糖・米なども入手したが、往時の遊牧民は基本的に自給自足に近い暮らし向きだったといわれる。
彼らの長い隊商行路は、交易路としての機能も果たしており、移動の途上でシーラーズなど都市の市場に家畜や織物を出荷し、必需品を買い求めていた。
社会構造
カシュガイ族は複雑な部族的ヒエラルキーを持つ社会である。
頂点に立つのは伝統的にイルハン(族長、カーン)と呼ばれる連合長で、歴史的にはジャニカーン朝と称する家系がこの地位を世襲してきた。
イルハンは全カシュガイ族を統率し、配下の主要部族(タイフェと総称される)を各部族長のカーンを通じて支配する仕組みだった。
カシュガイ族は五つの主要部族(アマレ、ダッレシュリ、カシュクル、大シーシュボルキ、ファルシマダン)からなり、それぞれに分家筋のカーンが存在した。
主要部族のほかにも複数の小部族があり、時代によって部族連合の構成員は変動した。
各部族はさらに多くの氏族・分枝(オボー)に細分化され、氏族ごとに「カドフダ」と呼ばれる長(年長の男性が務める)が置かれる。
この氏族長はかつては部族長カーンによって任命されていたが、氏族内の評議で推す有力者が充てられるのが通例だった。
カシュガイ族社会では「白髪ひげ(アーク・サガール)」と呼ばれる長老たちの発言力が大きく、氏族長や部族長も長老層の合意形成を重んじる習慣があった。
伝統的な紛争解決も、まずは一家・親族内で話し合い、それで解決しなければ氏族長や部族長、最終的には連合長が仲裁する階梯制が機能していた。
20世紀後半以降、政府の介入によって部族長会議は公式には解体され、現在では国家行政の末端機構(村長や評議会)に置き換えられているが、依然として非公式に長老たちがコミュニティ内で強い影響力を保っている。
家族形態は父系制で、カシュガイ族は父方の氏族名や家系によって身分や帰属意識が形作られる。
各人は父系の名乗り(オタック)を持ち、父系血縁集団が社会単位の基礎となる。
ただし婚姻によって母方・姻戚の繋がりも張り巡らされるため、個人は複数の血縁ネットワークに属して関係を維持している。
結婚は基本的に家同士の取り決めで若いうちに行われ、20世紀末までは男性は十代後半〜20代前半、女性は初潮を迎えてすぐの十代前半で嫁ぐ例が多かった。
好ましい結婚相手は父方のいとこ(パトリラテル・パラレル・カズン)で、同じ氏族・血族内での婚姻(族内婚)が伝統的に重視されてきた。
一夫多妻はイスラム法上可能だが、実際には経済的負担も大きいため一般には一夫一妻が主流である。
婚姻に際しては、花嫁の家に財貨を贈るブライズプライスの習慣があり、絨毯や家畜が贈与される。
結婚後、妻は夫の実家の天幕に入り同居するのが通例である。
こうしてひとつの天幕には祖父母・父母・子ども世代の大家族が暮らし、とりわけ末息子は「炉辺の子」として妻子とともに両親の最期まで面倒を見る役割を担う。
子が成長し経済的に自立できるようになると、両親から財産分与(前渡し相続)を受けて独立の天幕・家計を構える。
娘は嫁入りの際に持参金として分け前を与えられ、息子たちも結婚や分家の際に家畜や織物などを受け取る。
こうした慣習により、親世代が没する前に実質的な遺産相続が行われるため、カシュガイ族ではイスラム法に定められた死後相続の原則(男子2倍・女子1倍の相続権)はほとんど適用されない。
男女の役割分担はあるものの、遊牧社会では互いの協力なしに成り立たないため、男女は比較的対等で補完的な関係にあると評される。
成人男性は主に外での仕事を担い、羊・山羊の放牧や水源・牧草の確保、農耕地の耕作、家畜や物資の市場取引、狩猟、季節移動時の隊列指揮、テントの設営などを受け持つ。
少年も幼少期から父について牧夫や駄獣の世話を学び、移動の際には騎馬で家畜群を先導する役目を果たす。
一方、女性は家庭内の諸仕事を切り盛りする責任者である。
幼い子どもの世話、食事の調理とパン焼き、天幕内外の清掃、水汲み、薪集め、乳搾りやバター攪乳、そして織物づくりなどが典型的な女性の仕事とされる。
少女たちは母や年長の姉に付き添いながら家事全般を覚えていき、家族の労働力として重要な存在である。
もっとも、移動や災害など非常時には男女を問わず出来る者が出来る仕事をこなすため、役割の固定は状況次第で柔軟に越えられる。
遊牧民において女性は家計生産の中核を担っており、その経済的貢献と経験知から「母親/妻」として高い発言力を持つ場合も少なくない。
特に織物製作は女性の専門領域であり、収入源にもなるため、女性たちは一家の財産管理や意思決定にも一定の影響力を有してきたといえる。
伝統社会では公的な場に出るのは男性長老が中心であったものの、私的領域では年長女性もまた一族の実力者「長老」として尊重されてきた。
宗教観と儀礼
カシュガイ族は民族的には多元だが、宗教的にはほぼ全員がシーア派イスラム教徒である。
もっとも、かつての遊牧生活において彼らは定住民のような組織だった宗教活動には熱心ではなかった。
1979年のイスラム革命以前、毎日の礼拝(サラート)やラマダーン(月暦断食月)の断食をきちんと守る者は少数派で、正式な祭礼行事もイスラム暦最大の祝祭である犠牲祭(イード・アル=アドハー)くらいしか一般的ではなかったとされる。
彼らは形式ばった信仰よりも内面の素朴な信心を重んじ、「我々遊牧民こそ偽りのない良きムスリムだ」という誇りを持っていた。
実際、カシュガイ族には歴史的に自前のウラマー(イスラム法学者)や聖職者階級は存在せず、多くの集団ではクルアーンの短章を暗誦できる年長男性が葬儀で経文を唱えたり婚姻契約書をしたためたりする程度であった。
巡回聖職者のムッラーやスーフィーの行者(デルヴィッシュ)らが時折キャンプを訪れて祈祷や説教を行うこともあったが、いずれも外部(都市部)から派遣される他民族の宗教者であり、日常的な指導者ではなかった。
結婚契約の公式な登録も都市の宗教裁判所に赴いて行う必要があったため、遊牧民にとって宗教行為は常に「外の世界」との関わりを伴うものだった。
こうした背景もあり、彼らの信仰心は大らかで実利的な面が強かった。
例えば、死者が出ると遺体が邪悪な霊に冒されないよう誰か(しばしば祈祷を行うムッラー)が付き添って見守り、近親者が集まるまで遺骸を決して一人にしないといった習俗がある。
遺体の水洗・白布での包殻(カフン)は親族が手厚く行い、男たちが担いで人里離れた墓地へ運ぶ。
埋葬後にはその場で簡素なクルアーン朗誦が行われるが、葬儀自体は質素なものだ。
埋葬後7日目と40日目には近親者がテントや家屋に集まって追悼し墓参するほか、1980年代以降はイスラム共和政体の影響でモスクでの集団追悼礼拝を追加する家も増えた。
彼らは都市部の人々から聞き伝えたイスラムの天国・地獄の観念を素朴に信じてはいるものの、遊牧民の世界観では死後の運命より現世での氏族や共同体の連帯の方が切実な関心事であった。
一方、カシュガイ族の日常生活において最も大きな意味を持つ儀礼は宗教的というより社会的なもの――すなわち結婚式である。
婚礼はカシュガイ族にとって最大の祝い事であり、大勢の人々が一堂に会するほとんど唯一の機会である。
伝統的な結婚式は三日三晩にわたって行われ、初日は近親者同士の挨拶や食事会、二日目に余興や宴が盛大に催され、最終日(三日目)に花嫁を実家から花婿のもとへ送迎する「花嫁行列」が執り行われる。
花婿の家(キャンプまたは村)が披露宴の会場となり、親族のみならず近隣の仲間も集まってテントを連ねて祝宴を囲む。
婚礼のハイライトは男女一緒になって輪舞するダンス、ズルナとドホールによる民族音楽の演奏、そして棒を持って戦士さながらに演舞する棒踊りといった余興である。
彩り豊かな民族衣装に身を包んだ人々が昼夜にわたり歌い舞う様子はまさにカシュガイ族文化の精華と言える。
しかし1979年以降のイスラム共和制下では、このような男女混ざった踊りや音楽演奏は「不道徳」と見なされ、公の場では禁止されてしまった。
それでも伝統を愛する人々は細々と習俗を守り続け、1990年代初頭に政治的抑圧が一時緩んだ際には結婚式に奏者を招き踊りを復活させる動きも見られた。
結婚式以外の通過儀礼としては、若夫婦が分家して新世帯を構える際に近親者と長老を招いてささやかな祝いの儀を行い、親から子へ家畜や織物を譲り渡す習わしがある。
また男児が生まれて3〜4歳頃になると割礼(スンナ)を施すが、これも親族が集まる小さな祝い事として位置付けられている。
このように、カシュガイ族の人生儀礼は大小あれど基本的に「祝い」の性格が強く、共同体の絆を深める機会となっている。
宗教はその一部において精神的支柱となりつつも、彼らの日常の営みと信仰心はきわめて密接に織り交ぜられているのである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ずいぶん長くなりました。後編に続きます。