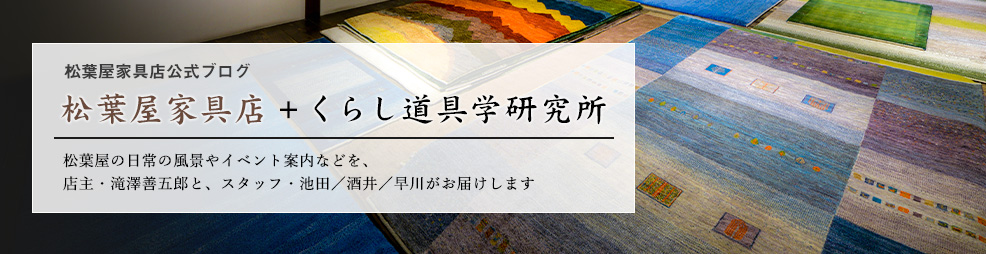松葉屋のなかの、三十脚ちかい椅子たち。

それぞれが、時を積み重ねてきた生きもののような顔をして、そこに並んでいます。
どうか、近くで見てやってください。
座面にそっと手を添えてみると、
浅い谷のように、あるいは船底のように、
やわらかなカーブを描いているのがわかるはずです。
もっと複雑なものもあります。
有機的で、どこか人の身体を思わせるような窪みと膨らみを持った椅子。
骨盤や太ももの裏、坐骨にそっと沿うような、
「木を削る」というより「木から引き出す」という感覚に近いのかもしれません。


なぜ、そんな形になるのか。
どのようにこのかたちをつくっているのか。
そのあたりのことも、ゆっくりと、ていねいにお話しします。
まるで椅子が、ひとつの風景になっていくような、
そんな時間をご一緒できたら嬉しいのです。
はじめに:長時間でも快適な椅子とは
木製の椅子で「長時間座っても疲れない」ために重要なのは、体に合った座面形状とその「削り込み(座ぐり)」です。人間の臀部や太腿裏は曲線で構成されており、座面の接触面積が広いほど体重が分散され、一箇所にかかる負担が減ります。
平らな板座に長く座ると、当たる箇所に圧力が集中し血行も悪くなるため、すぐに体を動かしたくなるものです。一方、身体のラインに沿った深い曲面の座面なら、自然な体圧分散が可能で、木の板とは思えない優しい座り心地を実現できます。
この記事では、ダイニングチェアを中心に、デスクワーク用や読書用の椅子にも共通する「疲れにくい座面」の形状と削り出しについて、職人の技術や人間工学の観点から詳しく解説します。
座面形状の種類と特徴
長時間でも快適に座れるかどうかは、座面の形状によって大きく左右されます。木製椅子の座面形状は大きく分けて以下のパターンがあります。
フラットな板座面(平面タイプ)
平らな板状の座面は構造がシンプルで見た目もすっきりします。しかしクッション性がなく体への当たりが点になりやすいため、長時間座ると臀部が痛くなりがちです。実際、「木の座面だと痛そう」という声も多く、平坦なままでは圧迫感で疲労につながります。

そのため従来は別途クッションを敷いて使われることも一般的でした。板座はへたりの心配が少なく手入れが容易といったメリットもありますが、長時間の着座には座面形状の工夫がないと負担が大きいことを覚えておきましょう。
お尻に沿う凹型座面(座ぐり加工)
座面をお尻の形に合わせて凹状に削り込んだものを「座ぐり」と呼びます。無垢の座板を大きく掘り込むことで、まるで座面が身体を包み込むようにフィットし、板座とは思えない快適さを生み出します。
深い座ぐり加工が施された座面では、臀部から太ももまで広い範囲で体重を支えられるため、着座時の体圧が均等に分散され血行不良も起こりにくくなります。実際に職人が丁寧に削り出した座面は、適度にお尻がホールドされるため前方に滑り落ちにくく、自然な姿勢を保ちやすいという利点もあります。


座ぐり加工された椅子に腰掛けた多くの人が「板座なのに驚くほど座りやすい」と感じるほどで、一度座ればその快適性に気付くでしょう。ただし凹みの深さには好みもあり、深すぎると逆に姿勢が固定される感じを受ける場合もあります。各メーカーで座ぐりの形状や深さは様々なので、ぜひ色々な椅子に座り比べて、自分に合ったフィット感を確かめてみてください。
緩やかな曲面座面(カーブ型)
フラットでもなく深い凹型でもない、中間的なカーブを持つ座面も多く存在します。座面全体が緩やかな曲線を描いていたり、エッジ部分を丸め込んだ形状で、見た目のシャープさを保ちつつある程度のフィット感を提供します。
例えば座面前方を下げたウォーターフォール形状(滝のような傾斜)もその一種で、太もも裏への圧迫を和らげ血行を妨げない工夫です。このタイプの座面は浅めの座ぐりとも言え、深い凹型ほどお尻を包み込みませんが、そのぶん体格や座る姿勢の違いに柔軟に対応しやすい利点があります。
緩やかなカーブ座面はデザイン上の美しさと一定の快適性を両立しており、近年の北欧デザインや日本の現代家具でも多く採用されています。長時間座る用途でも、前縁をしっかり丸めた曲面座面であれば太腿への食い込みが少なく、疲労感を軽減できます。


座面の削り出し技術:職人技と最新加工法
木製椅子の座面を人間の体に合う形に成形するには、高度な加工技術が必要です。その手法は大きく職人の手仕事によるものと、機械を用いた加工によるものに分けられます。
手作業による削り出し
伝統的な家具工房では、鑿(のみ)や鉋(かんな)などの手工具を使って座面を彫り込んでいました。特に「四方反り台鉋」という座面専用の鉋や、丸ノミ・スクレーパーなどを駆使し、職人が感覚を頼りに少しずつ曲面を削り出します。
手作業では木目の硬さの違いを感じ取りながら微調整できるため、身体に沿った絶妙なカーブを生み出せるのが強みです。ただし大変な重労働で時間もかかるため、その分コストも高くなります。例えば硬いオーク材の座ぐりを手鉋で削る作業は腕や肩に相当な負荷がかかるそうです。
熟練の職人が手間ひまをかけて仕上げた座面には独特の滑らかさと温かみが宿り、「座り心地の究極」を表現しているとの声もあります。
機械加工による削り出し
現代ではルーター(電動トリマー)やCNC加工機によって座面を効率よく成形する方法も普及しています。治具で固定した座板にルーターでパターン加工を施したり、3Dデータを用いてNCルーターで精密に彫り込むことで、職人の勘に頼らずとも再現性高く座ぐり加工が可能です。
実際、岐阜県飛騨のメーカーなどでは高度な専用機械を導入し、計算されたカーブを高速かつ高精度に削り出しています。日本で本格的な座ぐり用マシンを使いこなしているメーカーは2~3社ほどと限られますが、そのおかげで品質の高い座り心地を持つ椅子を低コストで提供できるようになったといいます。
機械加工後は最終的に職人がサンダーや鉋で表面を丹念に磨き上げるため、手仕上げの滑らかさも損なわれません。このように機械と職人技の融合により、現代の木製椅子は高いフィット感と生産性を両立しています。
なお、座ぐり加工の有無で座り心地は大きく変わります。無垢板を削り出す手間が増える分、椅子の価格も上がりがちですが「痛くない・疲れない板座」は良い椅子の証とも言われます。
各メーカー・工房とも工夫を凝らした加工法で理想の曲面を追求しており、その製作風景はYouTubeなどでも紹介されています。木工好きの間では、手掘りか機械掘りかといった違いも話題になりますが、最終的には座ったとき気持ちよいかが何より大切です。ぜひ加工方法にも注目しつつ、実際の座り心地を体験して選びましょう。
人間工学から見る「疲れにくい座面」の条件
座面形状と削り込みが体にもたらす効果を、人間工学の視点から整理すると以下のようになります。
体圧分散の効果
座面と体が接する面積が広いほど荷重が分散し、一点あたりの圧力が低減します。深い座ぐりや立体曲面の座面は臀部全体で体重を受け止めるため、平均圧力・ピーク圧ともに低く抑えられ、長時間でも局所の疲労や痛みを感じにくくなります。
実験的にも、背もたれを含め身体全体で支える姿勢をとることで、従来椅子より平均圧が有意に低下したとの報告があります。つまり、お尻や太ももへの当たりが柔らかく均一な椅子ほど長時間快適に座れるのです。
骨盤を支え姿勢を安定
人は座ると骨盤が後傾しがちですが、座面形状によってはそれを防ぎ正しい姿勢維持を助けます。例えば前縁がなだらかに傾斜したウォーターフォール形状の座面は、骨盤が自然に起きた姿勢になりやすく、背筋を伸ばして座れる効果があります。
座面後部が僅かに盛り上がった形状やお尻のくぼみに沿う座ぐりも、骨盤・腰まわりを安定させ、深く腰掛けても姿勢が崩れにくいです。また適切な座面高さ・奥行きとの組み合わせで足裏もしっかり床につき、骨盤から背骨にかけて無理のない姿勢を長く保てます。要は、体にフィットする座面は自然と良い姿勢に導き、筋肉の緊張を和らげてくれるのです。
太もも裏の負担軽減と血流
長時間座ったとき脚が痺れる原因の一つが、座面先端による太もも裏の圧迫です。人間工学に基づいた椅子では、座面の前縁を丸めたり傾斜させたりして、この圧迫を避けるデザインが採用されています。
前述のウォーターフォールエッジは典型で、座面が太腿のカーブに沿って前下がりになるため血流を妨げません。木製椅子でも座面前部を大きく面取りしたり、中央を低く両端を高くする「鞍型(くらがた)」座面にして腿裏への当たりを減らす工夫が見られます。
実際、手術用チェアなど特殊な椅子でも「腿裏を圧迫しない座面形状」にこだわった製品が開発されており、長時間でも下肢の血行が保たれることが重視されています。太もも裏に指2本程度の隙間ができる奥行き・形状が理想とも言われ、座面選びでは前縁形状にも注目すべきでしょう。
以上のように、座面の形状ひとつで着座時の体への負担は大きく変化します。「長く座っても疲れにくい椅子」とは裏を返せば人間の体の曲線に寄り添った椅子であり、平坦な板では得られない快適さがあるのです。
快適性を求めた座面デザインの進化と事例
木製椅子における座面デザインは、時代とともに快適性を求めて進化してきました。昔ながらのダイニングチェアやスツールでは、座面が平板でクッションを載せて使うものも多く見られました。しかし欧州のウィンザーチェアなど18~19世紀頃から木の座面自体を凹ませる工夫が現れ、職人たちは手工具で座板を削り出して「尻当たりの良い椅子」を作り上げてきました。
画像5ウィンザーチェア
20世紀に入ると、北欧デザインや日本の家具デザイナーたちも座面の曲線に配慮した名作椅子を数多く生み出しています。例えばデンマークの名匠ハンス・J・ウェグナーは座面前縁を大きく削ぎ落としたデザインを取り入れ、美しい曲線と実用性を両立させました。また、日本でも秋田木工や飛騨産業などが曲木や削り出し技術を活かし、和洋折衷の快適な椅子を製作しています。
特に近年の国産メーカーは、職人技と科学的アプローチを融合させて座面快適性を追求しています。前述した飛騨・高山ウッドワークスの椅子はその代表例で、コンピュータ制御の座ぐり機械と熟練工の手仕上げによって、誰が座っても心地よいカーブを実現しています。
一例として高山ウッドワークスのコムバックチェアは


「板座でも痛くない・疲れない」を体現した椅子であり、実際に座るとお尻に吸い付くようにフィットして木の硬さを忘れるほどです。座面が身体に絶妙に馴染むことで、食後の団らんや読書のひとときも疲労を感じにくく、ゆったりと過ごせます。まさに「長時間座っても疲れにくく、寛ぐのにも最適」な椅子として高く評価されています。
他にも、国内家具メーカーの製品には、美しい造形と座り心地を両立させた座面デザインが数多く見られます。例えば松葉屋でたくさんの方にご支持いただいている「キャプテンチェア」などは座ぐり加工によりお尻が適度に固定され、どの位置に座っても自然な姿勢がとれると評価いただいています。


実際に「木の椅子のイメージを覆す座り心地良さ」と評されるそれらの椅子は、長時間座っていても疲労感が少なく、多くの愛好家から支持を集めています。座面だけでなく背もたれの曲線やアームの形状まで含め、人間工学に基づいてトータルに設計された椅子が増えてきたことも、見逃せないトレンドです。
さらに最近では、高齢者向けやオフィス向けに医学・工学の知見を取り入れた椅子も登場しています。例えば建築×工学×医療の共同開発による高齢者用チェアでは、座面クッションの立体形状で座圧を分散しつつ骨盤を支えることで、長時間座っても腰やお尻の負担を大幅に減らしています。
オフィス家具大手オカムラが開発した手術支援ロボット用チェア「クンペル」でも、腰を包み込む背もたれと腿裏を圧迫しない座面形状を採用し、執刀医が長時間でも快適に座れるよう工夫されています。これらは用途は違えど、「座面形状を工夫して疲労を軽減する」という点で共通しており、椅子作りにおいて座面デザインがいかに重要かを物語っています。
おわりに:快適な椅子で豊かな暮らしを
椅子というものは、道具でありながら、ひとつの風景でもある。
その真ん中に腰かけたとき、背中がふっとゆるみ、気持ちが静まっていく。
とりわけ、座面。
じかに体が触れるこの部分には、椅子という存在の本質が潜んでいる気がする。
日常的に、僕らは知らず知らずのうちに長い時間を椅子に体を預けている。
とくに四十代、五十代、六十代。
ダイニングでゆっくりお茶を飲む時間が増えたり、書斎で本のページをめくる時間が伸びたり、
座っているうちに、その椅子が自分の体に馴染んでくるかどうか、
いつのまにか、体は正直にそれを測っている。
木の椅子がふっと暮らしを支えてくれる。
しっかりと、静かに。
削られた座面のカーブが、あなたの骨盤や太ももにそっと寄り添ってくれる椅子。
深く腰をかけても疲れにくい椅子。
そういう椅子が一脚あるだけで、暮らしの手触りが変わってくる。
「座面が、あなたの体に合っているか」
「どれくらい深く削られているか」
そんな視点で椅子と向き合ってみるのも、案外大切なことかもしれません。
一脚の椅子が、人生の静かな伴走者となってくれること。
ささやかな奇跡を、暮らしのなかに迎え入れる。
それが、椅子を選ぶという行為の本当の意味かもしれません。
きもちのいい椅子が30脚ちかく、店のあちらこちらに。
どれがいちばんかは、あなたのからだが決めます。
ためしに、いくつか座ってみてください。
椅子とあなたがぴたりと重なる瞬間が、きっとあります。