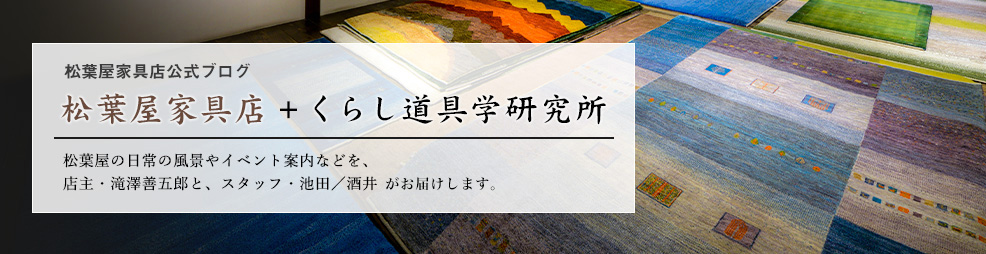ギャッベの向こうにある風景
こんにちは。 長野・大門町の、松葉屋家具店、滝澤善五郎です。
気がつけば、ゾランヴァリのギャッベとお付き合いをはじめて、もう二十年近くになります。 この間、僕たちが選んだ一枚一枚を、二千人近くのお客さまが、それぞれの暮らしに迎え入れてくれました。

玄関に。 リビングに。 寝室に。
時には赤ちゃんの遊び場に。


けれども、ある日ふと思ったのです。 この敷かれた一枚の向こうに広がる風景を、僕らはどれだけ見てきたのだろう、と。
ギャッベのふるさとは、イランの南西部。 ザグロスの山々を遊牧する、カシュガイの人びと。 草原の風にそよぐ羊の毛を、紡ぎ、染め、結ぶ。 その繰り返しの中で、ただ一つの模様が浮かび上がっていく。

僕も一度だけ、旅をしたことがあります。 乾いた大地に張られたテントを訪ね、 定住した家では食事をごちそうになり、 織り子の手元をただ黙って見つめていました。
またある時には、ゾランヴァリさんご兄弟や、 カシュガイのソマイエさん、プーランさんと
アリさんが長野を滞在して、 僕たちの店の一角で、ギャッベを織り上げてくれたこともありました。
今でも時おり、あの指先の動きを思い出します。
沈黙の中に響く、糸を結える音。 手が結ぶ小さな結び目ひとつひとつに、遠い土地の時間が宿っていました。
一枚のギャッベの向こうにある、 風と土と、家族と、記憶のこと。
今回はカシュガイ部族連合、その中でも特に織物技術において高い評価を受ける「カシュクリ族」についてお話しします。 断片的な体験と記憶、耳にした話、読みかじった資料を頼りに、 もう一度、ギャッベを生んだ人びとの暮らしと文化について、 ゆっくり、言葉にしてみたいと思います。
カシュガイ部族連合、高品質の織物で知られる「カシュクリ族」
イランの南西部、ファールス州の山々と平原を季節ごとに移動するカシュガイ部族連合。その中でも特に高品質の織物で知られるのが「カシュクリ族」です。松葉屋家具店では、こだわりの自然素材と伝統的な手仕事から生まれる本物のギャッベをご紹介していますが、今回はその中でも特に評価の高いカシュクリ族の織物文化に焦点を当ててみましょう。
歴史と伝統が織りなすカシュクリ族のギャッベには、何世紀にもわたって受け継がれてきた技と美が宿っています。彼らの手による一枚一枚の敷物には、遊牧の厳しい自然環境を生き抜いてきた人々の知恵と美意識が詰まっているのです。



カシュクリ族の起源と歴史的背景
多様な起源:多民族的背景と集合体としての形成
遊牧民の歴史は移動の歴史です。カシュクリ族が属するカシュガイ部族連合は単一の民族集団ではなく、様々な起源を持つ部族の連合体です。伝承ではカシュガイの族長層は11~12世紀頃に中央アジアからイラン高原へ移住してきたオグズ系のトルコ語を話す遊牧民と言われていますが、部族連合の大多数は16世紀以降に南ペルシアで徐々に結集した多様な起源を持つ集団と考えられています。その名の由来は定かではありませんが、長い歴史を通じて独自の文化と言語を発展させてきました。
伝承によれば、カシュガイの族長家の祖先はモンゴル帝国時代の13世紀にイランへ到達し、コーカサス地方(現在のアゼルバイジャン南部、アルダビール周辺)に定着したと言われています。その後、16世紀前半にサファヴィー朝のシャー・イスマーイール1世の要請で南部の防衛にあたるため、現在のファールス地方へ移住したという歴史があります。
興味深いことに、この伝承では彼らはかつてティムールに勝利した白羊朝(アク・コユンル)の部族の末裔とされています。白羊朝はその名の通り、白い羊を象徴とするトルコ系遊牧民の王朝で、15世紀に西アジアの広大な地域を支配していました。この中央アジアからコーカサスを経て南下した歴史的背景が、族長層の文化的アイデンティティに大きな影響を及ぼしているのです。
言語と宗教:アイデンティティの根幹
カシュガイ族全体は自らの言語を「トルキ」と称するトルコ系言語(オグズ語群)を話し、その言語はアゼルバイジャン語の方言に近いとされています。「ガシュガーイー語」とも呼ばれるこの言語は、系統的にはアゼルバイジャン語やトルコ語と近縁関係にあり、日常的な会話はトルコ語話者同士で概ね通じるほどです。
特徴的なのは、カシュガイ語には固有の文字体系がなく、公式の場ではペルシア語(ファールシー語)を用いることです。現在でもカシュクリ族を含むカシュガイ諸部族はペルシア語と併用しつつ、このオグズ系の母語を維持しています。家庭内や部族民同士では依然としてトルコ系の母語が話されており、口承の民話や歌謡、日常の呼称などに伝統言語が息づいています。
宗教的には、カシュガイはシーア派イスラム教徒です。これはイランの多くの少数民族がスンニ派や非イスラム教であるのに対し、多数派と同じシーア派に属する点で特徴的です。この宗教的共通性は、彼らがイラン社会の中で独自性を保ちつつも、一定の融和を実現できた要因の一つとなっています。
遊牧生活ゆえに、定住農村のようなモスク中心の宗教活動は少なく、過去には自前の聖職者をほとんど持たず、巡回するデルヴィッシュ(托鉢修行僧)や行商人に祈祷や儀礼を依頼する慣習もありました。例えば結婚契約の作成や葬祭で聖典の一節を唱えるといった宗教的所作も、都市部から来た聖職者に頼ることが一般的でした。しかし現代では定住化と教育普及により、他のイラン人と同様に地元のモスクや宗教行事に参加する機会が増えています。
カシュガイ部族連合における位置づけ
カシュガイ部族連合は伝統的に5大部族(アマレ、ダレシュリ、カシュクリ、シシュブロキ、ファルシマダン)と複数の小部族によって構成されてきました。中でもカシュクリ族は有力な部族の一つで、特に20世紀前半には部族連合内で大きな比重を占めていました。
歴史資料によれば、1963年時点でカシュクリ族(ボゾルグ派)は約4,862世帯を擁していたとの記録が残っています。当時の首長直属のアマレ部族が約6,000家族、ファルシマダン族が1982年時点で2,715家族(約12,394人)と報告されていることを考えると、カシュクリ族はカシュガイ部族連合内でも主要かつ大規模な部族だったことがわかります。
カシュガイ全体の人口は正確な統計がないものの、20世紀後半の推定で約50万人規模(資料によっては80万人とも)と見積もられています。この人口の大半は1960年代以降に定住化しましたが、21世紀現在でも一部は季節的な移動放牧を続ける半定住・遊牧生活を営んでいます。
カシュクリ族の内部構造と政治的変遷
ボゾルグ派とクチュク派:分裂の歴史
歴史的経緯から、カシュクリ族は「カシュクリ・ボゾルグ」(大カシュクリ)と「カシュクリ・クチュク」(小カシュクリ)という二派に分かれています。この分派は第一次世界大戦後の内部抗争に起因する興味深い歴史があります。
第一次大戦期、カシュガイ部族連合を率いるイルハン家のソラト・オッ・ドウラに対し、カシュクリ族の族長たちはイギリス側を支持して対立する立場を取りました。当時のイラン南部では列強の影響力が入り乱れ、部族の利害も複雑に分かれていたのです。戦後、勝利したソラト・オッ・ドウラは反逆したカシュクリ族への報復措置を行い、反対派の族長を解任したうえで部族の分割と弱体化を意図した政策をとりました。
具体的には、当時イルハンに忠誠を示していた一部のカシュクリ族集団を本体から切り離し、独立した小部族として再編したのです。それがカシュクリ・クチュク(小カシュクリ)族およびガラチャイ(Qarachahi)族の成立であり、残された本体がカシュクリ・ボゾルグ(大カシュクリ)族と呼ばれるようになりました。
この措置によりカシュクリ族は事実上三つの部族に分かれ、従来の「カシュクリ族」はその最大派閥であるボゾルグ派を指すようになりました。ボゾルグ派は前述のように1960年代に約4,800世帯を数え、カシュガイ部族連合内でも屈指の規模を保っていました。内部にはベグディリ(Begdili)氏族やジャマ・ボゾルグ氏族など複数の氏族集団を含み、こうした氏族は他の近隣部族(例:コフギルエ地方のアガチェリ族)との歴史的な結びつきも持っていました。
一方のクチュク派やガラチャイ族は相対的に小規模で、ボゾルグ派から分離された後はカシュガイ連合内の小部族の一つとして位置付けられています。
近代国家と遊牧民の対立
20世紀のイラン近代国家形成過程において、カシュガイ遊牧民は時に政府と対立し、時に協力する複雑な立場にありました。パフラヴィー朝のレザー・シャー(在位1925–1941)は遊牧民の政治的自立を抑え込むため、全土の遊牧民に強制移住と家畜没収を命じ、カシュガイ連合も一時解体状態に追い込まれました。
この過程でカシュクリ族も移動の自由と経済基盤を奪われ、族長層は政府に出頭するか地下に潜ることを余儀なくされました。1941年にレザー・シャーが退位するとカシュガイ諸部族は再び放牧生活と部族組織を復活させ、第二次大戦後にはイルハン家のもと連合の再統合が進みました。
モサッデク政権期(1951–53)にはカシュガイは政府寄りの姿勢を見せたものの、その後のパフラヴィー朝下では再び対立が深まります。1962年、政府の土地改革に反発したカシュガイ部族連合は武装蜂起するも鎮圧され、イルハン家のホスロー・ハーンら族長たちは亡命に追い込まれました。以後、帝政下ではイルハン不在のまま部族組織のみが存続し、多くの部族民が半定住化していきました。
革命後の変容と現代の状況
1979年のイラン革命後、亡命先から帰国したイルハン家のホスロー・ハーン・ジャニハニは旧支配地への復権を図り、カシュガイの遊牧民たちを率いて新政権に対する反乱を試みました。しかしこの蜂起も1982年に敗れ、ホスロー・ハーンは処刑、他の族長も投獄や再亡命を余儀なくされました。
こうしてカシュガイ部族連合は政治的指導者を失い、伝統的な部族統治機構は事実上終焉を迎えました。それでも部族としてのアイデンティティそのものは消滅せず、部族民たちは地元において非公式に長老や元族長の助言を仰ぎつつ内部問題の解決を図っています。
現代イランの中央政府はカシュガイを含む遊牧民を政治的には脅威と見なしつつ、一方で文化的には「魅力的な民俗遺産」として位置付ける複雑な姿勢を示しています。1970年代以降の強制定住化政策により、かつては完全な遊牧生活を送っていたカシュガイの人々の大半は現在、都市部や村落に定住し、一部が季節的な移動を行う半定住状態にあります。伝統的な遊牧生活そのものは縮小傾向にあり、イルハニ体制という部族連合の統治システムも崩壊したものの、今日でも文化的アイデンティティと織物などの伝統工芸は維持されています。
このような複雑な歴史と政治的変遷を経験しながらも、カシュクリ族は織物技術を磨き続け、カシュガイ部族連合の中で文化的に重要な位置を占め続けてきました。彼らの織物は単なる日用品ではなく、激動の時代を生き抜いてきた民族の誇りと創造性の表現なのです。
遊牧生活と社会構造
季節移動と生活の知恵
カシュガイ部族連合の人々、特にカシュクリ族の生活は羊や山羊の放牧を中心とする遊牧生活に根差しています。標高差のある地形を活かし、冬は暖かい低地(ガルムシール=温かい地域)で、夏は涼しい高地(サルドシール=冷たい地域)で過ごす季節移動は、彼らの生活様式の根幹をなしています。
春と秋には、数百キロに及ぶ移動ルート(イール・ラー)を家畜とともに移動します。この移動は単なる季節の変化に対応するだけでなく、羊や山羊に最適な牧草地を確保するための戦略でもあります。カシュクリ族を含むカシュガイの遊牧民たちは、山々の気象パターンや植生を熟知しており、どの時期にどの場所で放牧すれば家畜が健康に育つかを代々の経験から学んでいます。
住居は移動式の黒いテント(黒帳/シャー・チャードル)で、山羊の毛織物でできた天幕は夏は風通しが良く冬は保温性が高い構造になっています。テント内部には織物の敷物や毛布が敷き詰められ、家財道具も織物や木製品など軽量で運搬しやすいものが中心です。
食生活は放牧する羊・ヤギから得る乳製品(ヨーグルト、バター、チーズ)や肉類が主体で、交易で入手する米や小麦粉を加えたシンプルな料理が伝統的です。遊牧の移動経路に果樹の多い地域が含まれるため、乾燥果物や野草も貴重な栄養源となってきました。
血縁を基盤とした社会構造
カシュクリ族を含むカシュガイ遊牧民の社会は、血縁を基盤とした複雑な構造をもちます。基本単位は父系の氏族(タイファ)であり、各人は父方の氏族名に属することで社会的身分や信用を得ます。同じ氏族内での婚姻(族内婚)が伝統的に好まれるため、人々は父系だけでなく母系や姻戚関係によっても互いに多重に結びついています。
いくつかの近縁家族は移動キャンプを共にしてオバ(oba)と呼ばれるテント集団を形成し、季節移動の際には安全のため複数のオバが隊列を組んで移動します。このような柔軟な集団編成は経済的協力や安全保障に役立ち、問題が起これば解消・再編も容易であることから遊牧生活に適応した社会原理となっています。一方、定住村落に移ったカシュガイの人々も、血縁や姻戚で固まった集落を新たに作る傾向があり、都市に居住する場合でも近親者同士で強固なネットワークを維持しています。
カシュガイ社会では年長者(「白ひげ」の長老たち)の発言権が強く、重大な意思決定や紛争の調停はかつては族長や下位長(カドフダ)だけでなく長老たちの合議によってなされてきました。この伝統的な意思決定方式は、現代においても部族内の問題解決に活かされています。
カシュガイ社会における「白ひげ(しろひげ)」と呼ばれる年長者たちは、公式な役職や称号ではありませんが、コミュニティ内で非常に重要な役割を担う、尊敬される長老の方々を指す敬称です。 「白ひげ」という言葉は、文字通り「白い髭を生やした老人」を意味し、多くの場合、トルコ語系の言葉で「アクサカル(Aqsaqal)」、あるいはペルシャ語で「リシュ・サフィード(Rish Safid)」と呼ばれます。これらは中央アジアやイランの多くの部族社会、遊牧民コミュニティに共通して見られる概念です。
婚姻と家族の絆
婚姻は父系内部でのいとこ婚が典型的で、特に父方のいとこ(父の兄弟姉妹の子供同士)の結婚が伝統的に理想とされました。歴史的には男性は十代後半から20歳前後で、女性は初潮を迎えて間もない10代前半で結婚する例が多かったですが、1980年代以降は教育や外部就労の広がりにより結婚年齢が男女とも上昇しています。
結婚後、夫となる男性は基本的に自分の父母が暮らすテントに妻を迎え入れる(父方居住制=パトリローカル)の形をとります。新婚夫婦はしばらく父母と同居し子供が生まれる頃まで生活を共にするが、経済的に自立できる段階になると近くに新しいテントを張って独立の家(オジャフ)を構える習わしです。
一家の最終的な財産相続もイスラム法の定める慣習とは異なり、息子たちは結婚して独立するときにあらかじめ父母から家畜や財産の分け前(嫁入り道具を含む)を受け取る「前渡し相続」の制度があります。娘も出嫁時に持参金として一部の財産分与を受けるため、結果的にイスラム法に定められた男女比(男子2:女子1)より平等に近い財産分配が行われます。末息子は結婚後も両親と同居し老後の世話をする代わりに、最後に残った財産の大半(末子相続)を継承する習慣もみられます。
このように家族・親族間の強い結束が社会の基盤となっており、家事労働や育児も一族ぐるみで助け合う伝統があります。子供たちは幼少期から年長の兄姉や叔父・叔母に面倒を見てもらい、遊牧や家事の技術を学んでいきます。身体が十分に成長すると男女の区別なく家畜の世話や採集、水汲みなど年齢に応じた仕事を与えられ、大人たちもそれを見守りながら生活技能を口伝で教え込みます。
織物文化:カシュクリ族の特色ある手仕事
遊牧生活と織物の結びつき
遊牧生活においては、所有物はすべて携帯可能で耐久性に優れたものでなければなりません。そのため、カシュクリ族の女性たちは、羊毛を使った織物づくりの技術を高度に発達させてきました。彼女たちの作る織物は日常品であると同時に芸術品でもあります。
テントで暮らし、移動を繰り返す遊牧民にとって、織物は単なる床敷きや装飾品ではなく、生活必需品でした。防寒、装飾、収納、運搬、交易といった様々な用途に利用され、硬い大地の上での生活を快適にする重要な役割を果たしています。
カシュクリ族の女性たちにとって織物制作は、単なる家事労働ではなく、自己表現や創造性を発揮する重要な場でもあります。母から娘へと技術や意匠が伝承される過程で、各家系や個人の独自性も生まれています。
カシュガイ内の多様な織物文化:部族間の特色
カシュクリ族の織物はカシュガイ部族連合内の他部族とは異なる特徴を持っていますが、基本的な織物技術や結び方の方法は共有されています。カシュガイ全体が高度な織物文化を持つ中で、カシュクリ族は特に素材選択の厳格さと織り密度の高さにおいて際立っています。
アマレ族はカシュガイ部族連合の首長(イルハン)の直轄部族であり、元々は他部族から選抜された勇士や奉仕者で構成されていました。その名も「働き手」を意味し、イルハンの親衛隊・従者として発達した経緯から他の部族のような単一の血縁集団ではありません。アマレ族は自前の族長家を持たず、イルハン家の当主が直接統括していたため、他部族とは支配・被支配の関係に立つ特殊な位置付けでした。彼らは織物よりも行政的な役割が強く、織物制作に特化した伝統は比較的少なめでした。
ダレシュリ族は歴史的に豊富な騎馬軍勢を擁し、19世紀から20世紀前半にかけて大きな軍事的影響力を持っていました。カージャール朝末期にはファールス地方の実権を掌握するほどで、20世紀初頭の族長ホセイン・ハーン・ダレシュリは「ソラト・オッ・ドウラ(国家の威光)」の称号を得てイルハン家と並ぶ地位を望んだとも伝えられています。彼らの織物には力強い意匠が特徴として見られます。
シシュブロキ族の名称はトルコ語で「六つの部族」を意味するとされ、内部にいくつかの氏族グループを含みます。彼らの織物は幾何学模様や染色の色合いに独自の傾向が見られます。
ファルシマダン族(別名エイムル族)は他の主要部族とは異なる出自を持つ可能性が指摘されています。彼らは自らの起源をハラジ(Khalaj)部族に求め、かつて中央イランのハラジェスターン地方から南下してきたと伝えています。幾何学的な紋様や細かな紋織りのキリムで知られており、カシュクリ族とはまた異なる個性を示しています。
このように、カシュガイ部族連合内の各部族は言語や宗教など大枠の文化は共有しつつも、出自伝承や経済基盤、対外関係、工芸の様式において微妙に異なる特徴を持ちます。カシュクリ族はその中でも織物の品質と部族規模で傑出し、アマレ族を除く他部族とは時に協力し時に競合しながら、連合内で重要な役割を果たしてきました。
カシュクリ族のギャッベ:品質と美を極めた織物
ギャッベとは何か
「ギャッベ」とは、イランの遊牧民が作る厚手の敷物のことです。遊牧テントの寒い床に敷くための実用品として発展したギャッベは、長い毛足と素朴な意匠が特徴で、床に敷いた時の快適さを重視した織物です。一般的に絨毯よりも結び目の密度が低く、厚みがあり、シンプルな意匠が特徴とされます。
素材選びへのこだわり
カシュクリ族のギャッベが高く評価される主な理由の一つは、素材選びの厳格さにあります。シラーズ周辺の山岳地帯で育つ羊の毛は特に柔らかく染料の発色が良いことで知られ、「イランでも随一の美しい光沢と深い色合いを持つ」と評されてきました。
専門家の間では「シラーズのウールほど美しく濃厚な発色を示す毛は他にない。その深い青と濃紅はまるで半透明のエナメルのように輝く」と絶賛されるほどです。カシュクリ族の女性たちはその中でも特に上質で長い春毛を厳選し、手触りや光沢、発色の美しさにおいて優れた織物を作り上げています。
遊牧民の羊毛は特に質が高いと言われますが、それは彼らの羊が自然の草地で健康に育ち、異なる標高を移動することで様々な栄養を摂取できるためです。低地の草原と高地の牧草地を季節ごとに移動することで、羊は多様な植物を食べ、それが毛質の良さに繋がっています。
カシュクリ族は羊毛の選別にも非常に細心の注意を払います。毛刈りの時期や羊の部位によって毛質が異なることを熟知しており、特に春の毛刈りで得られる柔らかくしなやかな毛を重視します。さらに、手作業で不純物を取り除き、最も質の良い部分だけを選り分けるというきめ細かな作業を行います。このような徹底した素材へのこだわりが、最終的な織物の品質を大きく左右しているのです。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA