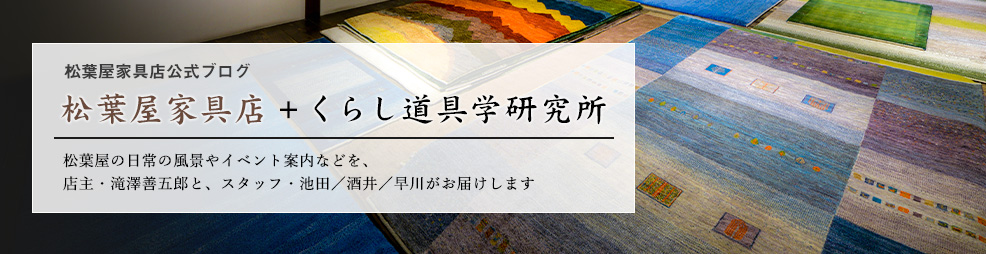こんにちは、松葉屋家具店スタッフの池田です。
少し前、梅雨の晴れ間に
白馬のスキー場で伐採されたミズナラの原木を見に
行ってきました。
大町市で林業を営む
「山仕事創造舎」さんから
大きなミズナラを伐採したので
見にきませんか?と
声をかけていただきました。
松葉屋では10年ほど前から
地域の材を使った家具制作を続けています。
そのことを知った林業関係の方や
お客様からご相談をいただいて
伐採現場に立ち会ったり
原木を選ばせてもらう機会も少しずつ増えてきました。
家具制作の材木を手にいれる場合は
製材された板材を材木屋さんから
選ぶのが一般的です
樹種や大きさで選んだり
場合によっては産地(⚪︎県産まで)を
選べる場合はありますが
細かい場所や
どんな経緯で伐採されたものなのかは
ほぼわかりません。
伐採された現場も人もわかるものは
私たちにとって
「顔の見える」貴重な材です。
さて、どんな木が見られるのかと
貴重な機会にワクワクしながら現場へと向かいました。

今回の伐採現場は
もともと昭和の前まで
薪炭林として利用されていました。
燃料としての利用がされなくなったことで
木が大きく育ちすぎて自重で倒れたり
雪の重みで折れたり
危険な状態にあった森林を
間伐をして、若返りをすることで
雪害に強い森林を作ることを目的として
スキー場を管理する
八方尾根開発さんの山を
山仕事創造舎さんが作業しています。
日本の多くの里山は薪炭林です。

炭の材料として利用されていた頃は
30年くらいで伐採して
運び出して
を繰り返しながら
森林の若い状態を保てていました。
年を取って大きくなった木は
倒木の危険だけでなく
樹液が出せなくなって、抵抗力が落ちて
ナラ枯れの原因となる虫に狙われやすくなると言います。
「ナラ枯れ」とは
カシノナガキクイムシが
ナラやシイ、カシの幹にせん入する際に
ナラ菌が樹体内に持ち込まれて蔓延し
道管を塞がれ樹木内の細胞が壊死することで
木が枯れてしまいます。
また、樹体内で成長・羽化した新成虫が体にナラ菌を付着させ、
別の健全なナラの個体に移動、せん入することで、
周囲に被害が拡大します。
この被害が拡大しないための対策として
被害を受けた樹木の燻蒸や
殺虫剤の注入
ビニールシート被覆による侵入予防
被害が拡大しやすい大径木の伐採による
森林の若返りを行うなど
対策がとられています。
林野庁ホームページ
ナラ枯れ被害についてpdf より
また、ナラ菌によって枯れた木は
被害拡大を防ぐ目的から
他の地域へ持ち出すことはできないため
伐採しても材料としての利用はできません。
今、長野県でも
「ナラ枯れ」が進んでいます。
今回の伐採現場も
これから被害を受ける可能性がある地域のため
森林の若返りと、材木の利用の観点からも
伐採をするタイミングだった
ということですね。
また、間伐した材木は
多くは薪として利用されるのですが
薪にする機械に入らない大きさの木だと
扱いにも困る場合があるそう。
伐採した人の
「大きいから薪にするのはもったいない」
という気持ち以外にも
「行き先がなくて持て余す」
ということも
松葉屋へ声をかけていただいた
理由のひとつだったのだなと
腑に落ちたのでした。
近年のキャンプブームで
薪がよく売れると聞いていて
材木の利用先ができてよかったなと思って
いたのですが
人がしばらく入らなかった山で大きくなった木は
そう簡単に利用できるものでもない。
という側面もあるようです。
材木として利用できるうちに
伐採をして森林を若返らせること。
薪にするには手に余る
大きな木もあるということ。
今まで行き先がなかった木が
「松葉屋なら何かに使ってくれるかも」
と、行き先になれたのなら
木材の利用のサイクルに
参加できたようで
とてもうれしいことです。


今回は、伐採した時期が
冬期ではなく
水をぐんぐん吸い上げている時期なので
これからの乾燥・製材の中で
どのくらい動くのか。
今の長野県の森林の現状と
いろいろな経緯で
ご縁があって出会ったミズナラです
じっくり時間をかけて
ミズナラの行き先を作っていきます。