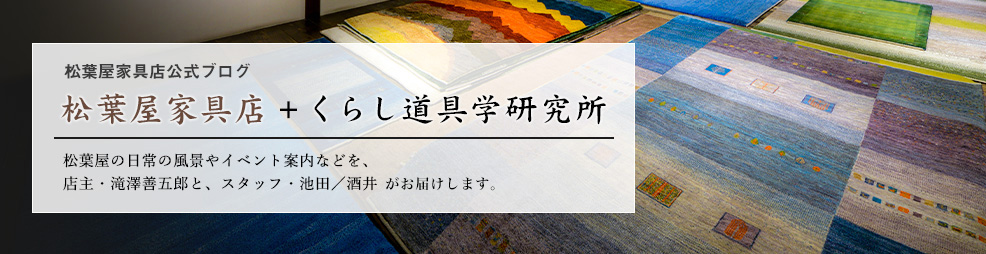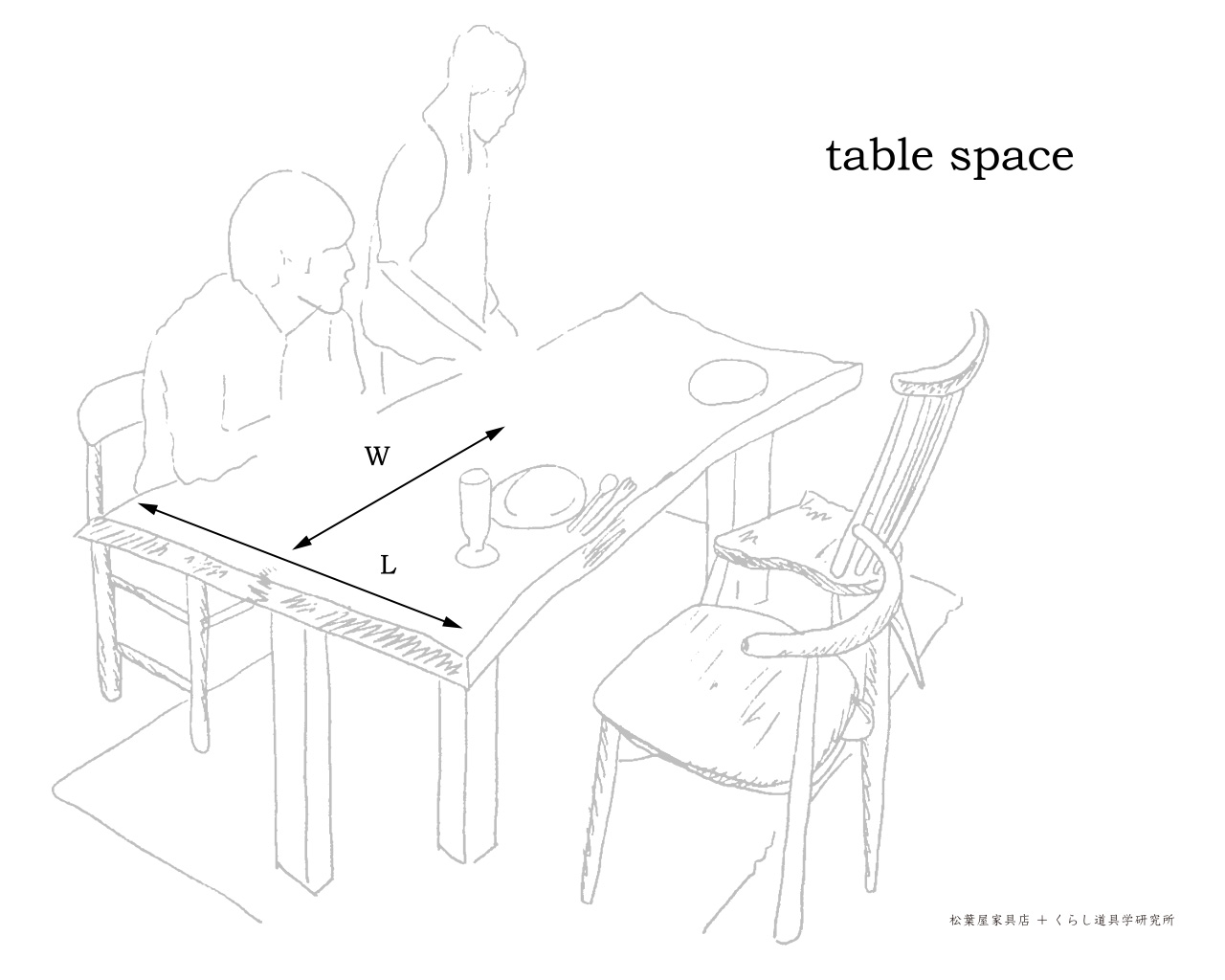こんにちは、スタッフの池田です。
森へいくツアー2日目の様子です。
前日の夜の「木ろうそく」の名残を残し
朝はすっきり晴れて
冷たい空気も気持ちのいい2日目の始まり。

夜は雨がザーザー降っていました。
朝はかまどでご飯を炊きます。

お釜から、ぶくぶくと沸騰する音が聞こえてきます。
お釜に耳をすましているのは
「なべさん」こと北村さん。
いつもツアーの時に大網の暮らしを教えてくれます。

沸騰する音が聞こえて・・・
それが聞こえなくなったら蒸らす。
美味しそうに炊き上がりました。


そして、美味しい朝ごはん。

「くらして」さんではお醤油もお味噌も作っています。
鮭の醤油漬けも、お味噌汁も、みんな元気になる味がしました。
食後は大網の村の中を歩きました。


炭焼きをしている釜

大網の森林で伐採した楢で、なべさん達が炭を作ります。
次は12月に炭焼きをするということ。
炭窯の中は人が3〜4人入れる大きな空間がありました。
周囲をぐるり、森林に囲まれた大網では
山の中にも炭窯の跡があったり
昔から炭作りを行なっていたそうです。
これまでの森へいくツアーでも、火鉢の炭にあたって暖をとったり、炭で焼いたお餅を食べたり
気づけば身近にありました。

その後、大網の森の中へ
くらしてさんが作る森の中の遊び場を案内していただきました。
冬に来た時は、雪で埋もれていた木で作った滑り台や
ながーいロープのブランコも。
ブランコは、すーっと森の中に飛び込んでいくようなちょっとしたスリルと
緑の中に浮かんでいるような気持ち良さがあって
大網の森の明るさを全身で感じられました。
みなさん、童心にかえってとっても楽しそうでした。


森の中で一息ついた後は
薪割りをします。

なべさんのお手本、お見事です。
皆もなべさんに習い、挑戦します。

重いなたを振り下ろして
パカンと割れた時は快感でした。
日も出てポカポカしていたので、全身運動の薪割りをすると
暑いぐらいです。
薪ストーブがあるというお家の方は、家でも薪割りをしているということで
身近な作業かもしれませんが、
初めて薪割りをした身からすると
最初は、こんなことで本当に割れるのか?!と心配になるような。
どこに力を入れればいいのかわからない、感じでした。
だんだんと慣れて、タイミングと腰を落とす姿勢と、持ち手のバランスと
うまくいくと綺麗に割れる。
木も節があると、なかなかスパッと割れずに苦戦するので、
節があって割れにくいっていうことは、繊維が入り組んでいるから
柱とかに使えば丈夫だっていうことなのかな・・・
など、ちょっとした気づきもあります。
松葉屋では家具にするための木の性質についてはよく考えるのですが
燃料にするために、木を割って、それが割りやすいかどうか
というのは触れたことがなかったので
少し新鮮な、木との関わり方でした。
さて、そんな重労働の後は
お楽しみのお昼ご飯と、大網といえば、の栃餅も
火鉢で焼いて、最後のおやつにいただきました。

薪割りはすごく重労働なので
道具もきっと、木を割りやすいように考えて
改良されてきた歴史もあるんだろうなあ、と思うと
木を燃料に加工するための「道具」のことも
やっぱり切り離せないなと感じました。
次回かその次か、木と道具の関係も、森へいくツアーでやってみたいテーマとして
上がっています。
木と火の関係から
煮炊きをする食べ物のことも
燃料に加工する道具のことも
木を燃やした煙の匂いも
こんなに意識したことはなかったかもしれません。
木は使い方で、見せる顔が全然違うんだな、と
家具材の見方も少し変わりそうです。
また、炭焼きや薪に木を使っていたから
木を伐り、森林の循環が起こり
健全な状態の山が保たれていたという側面もあるようです。
これは、また、炭焼きのことを詳しく聞きにいく予定があるので
そのときに。
次回のツアーは6月上旬頃を予定しています。
新緑の緑が眩しいときに
また「木と◯◯」やります。